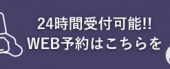1セミリンの恐怖
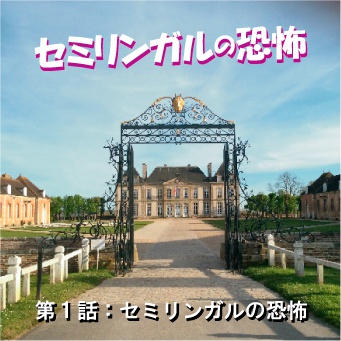
第1話・セミリンガルの恐怖
英国人と結婚して、今はフランスに住む私は子供達を「仏語、英語、日本語」の3ヶ国語で育てています。「羨ましい」と言う人も多いですが、私自身は「子供に惨い事を強いている」と思っています。
何故なら、私は自分自身が語学の習得には随分と苦労したので、それがどんなに大変な事であるのかは自分でもよく知っているからです。
また、この環境は下手をすると子供を「母国語を持たないセミリンガル」にしてしまう危険性が高い事をも私は十分に自覚しています。
語学は伝染病ではありませんから、本人が努力しない限り絶対に上手にはならないのであり、それは子供とてまったく同じ事です。
私が「セミリンガル」という言葉を始めて知ったのは大学の教育心理学の授業の時でした。教授によれば、「バイリンガルの子供は知力の発達が遅れる。
何故なら、人間は言葉を使って物事を考えるからで、習得言語を2つに広げると両方の言語の発達程度が低くなるので、難しい問題を考えようとする時にどちらの言語の発達も未熟となって、頭が混乱してしまう」という事でした。
そして、「人間の知能は母国語の発達に従って発達していくのだから、まずは母国語を持つ事が一番大切です。母国語の発達は知能の発達だけでなく、性格形成などにも大きく関わってくる」という事でした。
多言語ができるようになる事は確かに良い事かも知れません。しかし、それを強いる事によって母国語を持たず、人間としての中身もないセミリンガルとなってしまうくらいなら、「バイリンガルになんて、ならなくてもいい」とすら私は思っています。
それでもなお、我が家ではそうせざるを得ない環境にあるという必然性から、敢えて子供にそうさせているに過ぎません。
だから親としては子供からの信号に敏感に気づいて、子供の成長に合わせて軌道修正する努力を怠らないようにする責任があると思っています。
長男が2歳半の頃、当時は英国に住んでいたのですが、ある日私は長男が自分の意思を上手に伝えられずイライラするようになっている事に気がつきました。
これは「日本語と英語が混ざってしまい、頭の中で混乱が生じ、自分の年齢相当の語学力を持てない事による苛立ちだ」と判断した私は、その日から子供に英語だけで話しかける事にしました。
私の中では、「子供に日本語を教えるのが、ちゃんとしたお母さん」という固定観念があったので、この選択は私にとっては最高の屈辱であり、自分自身の挫折でもあり、苦しい選択でした。
でも敢えてそれを選択したのは、「今、この子にとって本当に必要な事は何なのかを考えた時、まずは年齢相当の母国語を与えてやる事であり、現在こうして英国に住んでいる以上、それは英語であるべきである」と判断したからでした。
こうして英語だけに言語を絞る事にした途端に長男の英語力はメキメキと上達し、自分の意思を表現する事ができるようになり、苛立ちも納まって行きました。
更に長男は英語が上達した事によって2つの別々の言語が存在する事をはっきりと認識したと見え、驚いた事に、それによって却って日本語力までもが上達したのでした。
語学間の距離の遠い「日本語と英語」では苦労した長男ですが、母国語が英語だったせいか、英語との語学間の距離が近い仏語の習得は極めて早かったです。
今ではちょっと見にはペラペラですし、学校の勉強にもついて行っているようなので、少しはホッとしているところですが、でも油断は禁物だとも思っています。
仏語は両親供が母国語ではないので、実際には子供がどの程度のレベルにいるのかを正しく判断するができないので、特に注意が必要です。
親が「うちの子は大丈夫」とタカをくくって子供からのサインを感じ取るアンテナをしまった日から、その子のセミリンガル人生が始まると思っています。
その時は大丈夫でも、学齢が進むにつれて変化する子供の状況を把握する必要があるものなので、親はアンテナを常に立てておかなければならないと思います。
我が家には3人の子供がいて、同じ兄弟と言えども、それぞれまったく違った性格、能力、個性を持っており、それぞれの年齢や能力、環境によって、まったく違った成長過程があります。
親のメンツよりも、その時その子供の成長にとって本当に何が必要であるのかを勇気を持って選択する事が、親としては何よりも大切な事なのだと思います。
筆:滝つぼ 2005年
2大人のセミリン
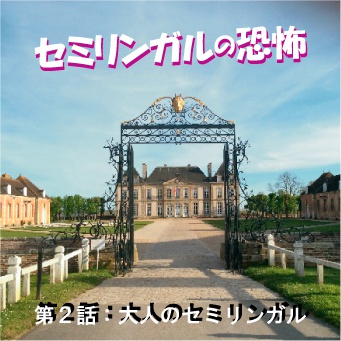
第2話・大人のセミリンガル
どの言語も発達が不十分で、きちんとした母国語をもたない事を「セミリンガル」と呼びます。では「セミリンガル」と「バイリンガル」の違いは一体何なのでしょうか。
これは私の持論ですが、「セミリンガル」は外国語を習得する発達段階において、誰もが多かれ少なかれ体験する現象であり、バイリンガルとセミリンガルは常に表裏一体の関係にあるように思います。
大学に入学するまで、英語など殆ど喋れなかった私の母国語は完全に日本語なのですが、そんな私でも一時的に「セミリンガル」みたいになった時がありました。
英語は苦手だった私が、何故か英文科に入学する事になってしまい、「よし、この大学4年間で、英語力をバッチリ身につけて卒業しよう。」と決意した私はESS(英語研究部)に入部して、徹底的な英語の勉強を突然開始しました。
こうして毎日、英語ばかり勉強しまくっているうちに、気がつけば私の日本語が何だかおかしくなっていました。
その頃の私は、「ガーバメントのポリシーがエフェクティブにファンクションすればポジティブなリザルトをアチーブできる。」と、こんな具合に、日本語の文法の中に英語の単語を当てはめているだけで、日本語でも英語でもない、わけのわからない「謎の言語」を発していたものでした。
これでもESSの人間同士ならば意思の疎通ができてしまうので、ついついこういう話し方が癖になり、そのうちに英語がまったくわからない人と話す時には、「えっと、日本語だったらなんて言うんだっけ?」と、頭の中でいちいち翻訳しなければ、日本語が出て来なくなってしまうような現象に陥っていました。
こうして私は、英語だって大してできもしないくせに、まともな日本語で話しをする事も難しく感じるようになっていたのです。
そんな時、教育心理学の授業で「セミリンガル」の事を始めて知った私は、自分が今、「セミリンガル状態」になっている事に、自分で突然気がつきました。
「これではいけない」と思った私は、その日から「自分の日本語力も同時に向上させなければ」と決意して、今度は片っ端から日本語の本をも読みまくりました。それと同時に日本語と英語を混ぜないで話しをするように心がける事にもしました。
こうした私自身の体験から言えば、「言葉が混ざる」という現象は、言語の発展が未熟な段階の時に起こるものであるように思います。
その後、自分の英語力が上達して行くのと比例して、私も英語は英語、日本語は日本語と、きちんと使い分ける事ができるようになって行ったものです。
ドイツ語も英語も両方とも通訳レベルにまでこなす才女のHさんは、数学も得意科目だったのだそうですが、彼女は「2桁の簡単な足し算ができなくなってしまった。」と話してくれました。
これは、ドイツ語では1の位と10の位を逆に言うので、簡単な2桁の計算をしようとすると、どっちの位がどっちだったのか、頭の中で混ざってしまうからなのだそうです。
ところが、これがもっと複雑な計算をする場合ともなれば、自分でも、「よし、計算するぞ」と力が入り、脳が日本語一色となるので、かえってすらすらと計算もできるのですが、楽しく会話をしている時などのように、気が緩んでいる時にふいを付かれると、頭が真っ白になってしまい、突如として「計算不能状態」に陥ってしまうのだという事です。
このように、大人でも一時的に「セミリンガル状態」に陥る事もあるものです。
しかし大人であれば、自分の脳がちょっと変な状態になってしまっても自分でその事に気づく事ができるから、自分で軌道修正をする事もできるものです。
それが子供の場合には自分で気がつくのは殆ど不可能なので、親がどこかで気づいてやらないと、次第にそれが脳の発達や性格形成にまで影響を及ぼし、やがてはもう軌道修正のきかない「本物のセミリンガル」となってしまう危険性も極めて高まる事になるのだろうと思います。
だからこそ、そういう環境を子供に与えた親の責任は重大であると言えるわけです。
「子供に良かれ」と思ってした事が、下手をすると恐ろしい結果を招く事にもなりかねません。
それゆえ親としては「バイリンガル教育」に関する正しい知識と十分な認識を持った上で、子供を正しく導いてやりたいものだと、つくづく思わされます。
2005年 筆:滝つぼ
3うちの子は大丈夫
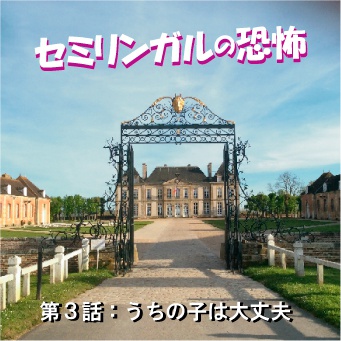
第3話・うちの子は大丈夫
うちの長男が2歳半になった頃、当時イギリスに住んでいた私は、初めての子供を「英語と日本語のバイリンガル」に育てる事に意欲を燃やしていました。
でも実際には長男の言葉は年齢より遅れ気味で、長男もそれで苛々している様子だったので、私も色々と悩み始めていました。
そこで私は先輩のお母さん達に色々アドバイスを求める事にしました。
ご主人が英国人で当時10歳位のお子さんを持つ先輩のMさんに相談したところ、Mさんは、「あら、でもAちゃん、まだ2歳でしょ? 心配ないわよ。うちの子なんて4歳になるまで一言も喋らなかったわ。」と笑っていました。
その先輩は自信をもって子育てをしておられる様子だったので、「えええっ!4歳まで喋らなかったんですか?!それってヤバくないですか??」などと、若輩者の私が口をはさむ事など、とてもできませんでした。
ご主人がドイツ人で英国に住んでいるSさんには3人のお子さんがいて「お子さん達を3ヶ国語で育てている」というのを自慢にしていました。
彼女とは日本語、父親とはドイツ語、学校では英語だがドイツ語の家庭教師もつけているという事で、特に一番上の5歳位の男の子はとても頭がいいとの事でした。
そうこうするうちに、その男の子が、3歳位の妹さんに暴力を振るい出したのです。
それも凄い勢いで怪我をするのではないかと思う程だったので、周りの人達も驚いたのですが、Sさんは「うちの子、ちょっと乱暴なの。いつもこうなの。」と話していました。
ご主人がイタリア人で英国に住んでいるNさんには男のお子さんが二人いらして、やはりお子さん達を3カ国語で育てている事を自慢にしていました。
特に上のお子さんは優秀で、有名私立にも合格し、3カ国語をきちんとこなし、礼儀正しくて感じもよく、私は心から関心しました。
そこへ下のお子さんが現れました。もう10歳以上であろうに、何だかちょっと挙動不審で変な感じです。
そのうちに何かの事で癇癪を起こし出して収拾がつかなくなり、その子は子供部屋に追いやられてしまいました。Nさんは「あの子はちょっと頭がおかしいのよ。」と言いました。
こんな風にチラッと垣間見ただけで、他所の子供の事を結論付けるのは傲慢な事だと思います。
また、どんな環境にいようと、生まれつき言葉の遅い子供も、乱暴な子供も、少し変な子供も、時には生まれて来るものですから、すべてを「バイリンガルで育てている事」と関連付けるのは短絡的な見方だとも思います。
でも少なくともうちの長男に関しては、生まれた時から毎日接して来た母親の私の意見を信用して頂けるなら、生まれつき穏やかな性格だった長男の当時の「イライラ現象」は、「バイリンガルで育てている事に対しての子供からのサインである事」に間違いはないと、私には確信する事ができたのです。
日本人の両親を持ち、日本に住んでいれば、日本人になる事も、母国語を持つ事も、普通に生活してるだけで取り合えずは誰にでも達成できる「人間として当たり前の事」です。
でも海外に住む子供達は、こうした「人間として最低限の権利を剥奪された過酷な環境」に生きているのです。
だからこそ、まずは親がその事を自覚した上で子供の教育方針を決定するべきであると私は思います。
2005年 筆滝つぼ
4バイリンに育てな

第4話・バイリンガルに育てなければ!
長男が2歳半になった頃、当時イギリスに住んでいた私は「子供をバイリンガルに育てたいという理想」と「実際の現実の難しさ」の板挟みとなって、苦しんでいました。
私の心の中では、「この子の言葉の発達がうまく行っていないという現実を潔く認めて、取り合えずは言葉を一つに絞り、まずは母国語を与えてやるべきなのではないか」という気持ちと、「いや、そんな事をしたら大変な事になる。」という恐怖感が、互いに激しく戦っていたのです。
「バイリンガルに育てるのがいいお母さん」という「固定観念」を持っていた私にとって、「バイリンガル教育を諦める」などという選択肢は「最高の屈辱」であり、「自分自身の挫折」であり、存在してはいけない事でした。
しかし、その一方で、大学の授業で教えられた「セミリンガル」という言葉への恐怖心も私の中で同時に育っていました。
確かに世の中には何ヶ国語でも簡単にできるようになる子供もいるものです。でも、一カ国語だけで育てていたって「言葉の学校」に通わないと満足に言葉ができるようにならない子供もいるものなのです。
こうして私なりに色々と苦しんだ末、「この子にとって今大切なのは年齢相応の母国語を与えてあげる事である。」という結論に達した私は、その日から長男に英語で話しかける事にしました。
こうして私なりに色々と苦しんだ末、「この子にとって今大切なのは年齢相応の母国語を与えてあげる事である。」という結論に達した私は、その日から長男に英語で話しかける事にしました。
そして、それを実行してみて、改めて、この「固定観念」は「私一人の勝手な妄想」だったのではなく、実際に世間もそう思っていて、「そうしない母親を世間は厳しく裁くものなのだ」という現実の厳しさを知ったのでした。
私が長男の言葉を英語だけに絞った事を夫の姉が聞きつけるや否や、義姉は、「母語とは母の言葉であり、あなたの言葉は日本語なのだから、あなたは子供を日本語で育てるべきだ」と言って、私に強く抗議しました。
私が長男の言葉を英語だけに絞った事を夫の姉が聞きつけるや否や、義姉は、「母語とは母の言葉であり、あなたの言葉は日本語なのだから、あなたは子供を日本語で育てるべきだ」と言って、私に強く抗議しました。
私は「ヨーロッパ人が起源を同じくする似たような言語を多数習得する事」と、「まったく言語形態の異なる日本語と併用する事」は根本的に違う事である事をいくら義姉に説明しても、義姉はまったく聞く耳を持ちませんでした。
またある時は、たまたま電車で向かい合わせたスペイン人が突然「あなたが日本人なら日本語で子供を育てるべきだ。」と言い出し、私に説教を始めました。
ご近所に住んでいた日本人の知り合いのお嬢さんは、当時9歳位だったでしょうか。日本人家庭ですが、駐在でイギリスに来たので、彼女は現地の学校に通い、言葉ができない事で辛い思いをしていつも泣いていたのでした。
またある時は、たまたま電車で向かい合わせたスペイン人が突然「あなたが日本人なら日本語で子供を育てるべきだ。」と言い出し、私に説教を始めました。
ご近所に住んでいた日本人の知り合いのお嬢さんは、当時9歳位だったでしょうか。日本人家庭ですが、駐在でイギリスに来たので、彼女は現地の学校に通い、言葉ができない事で辛い思いをしていつも泣いていたのでした。
それでも、「バイリンガルになる事が大切なんだから」と親から言われ、子供ながら辛い事もじっと我慢して頑張っていた彼女でした。
そんな彼女が我が家に遊びに来ました。長男と遊んでくれていた彼女は、しばらくすると長男が日本語ができない事に気がつきました。
そんな彼女が我が家に遊びに来ました。長男と遊んでくれていた彼女は、しばらくすると長男が日本語ができない事に気がつきました。
私が「ごめんね。Aちゃんは日本語ができないのよ。」と言うと、彼女は顔面蒼白となり、「えっ!で、でも、子供をバイリンガルに育てなければ!」と私に向かって、そう叫んだのでした。
2005年 筆・滝つぼ
2005年 筆・滝つぼ
5バイリンの心の傷
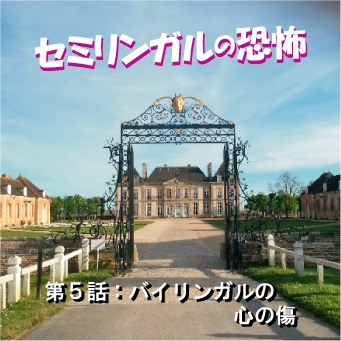
第5話.バイリンガルの心の傷
私が「英語だけで子供を育てている」と知った途端、私に向かって「子供をバイリンガルに育てなければ!」と叫んだ9歳の女の子の顔は、今でも私の心に焼き付いています。
「みんなの言っている事がわからないし、自分の言いたい事も言えないで、どうやってお友達を作るの!」と言って泣きながら学校に通っていた彼女。
「バイリンガルになる事はどんなに辛い事があっても絶対に達成するべき事である」と信じて、子供ながら頑張ってきた「バイリンガル信仰」が、根底から覆えされた思いがしたのだろうと思います。
かつて上司だったNさんは某有名大学卒業なのですが、「下からの持ち上がりだった上、大学時代はサッカーに明け暮れて、友人達のノートのお陰で卒業できただけなので、自分にはその学歴に見合うだけの実力がない!」という事を自慢にしている気さくな方でした。
かつて上司だったNさんは某有名大学卒業なのですが、「下からの持ち上がりだった上、大学時代はサッカーに明け暮れて、友人達のノートのお陰で卒業できただけなので、自分にはその学歴に見合うだけの実力がない!」という事を自慢にしている気さくな方でした。
そんなNさんの奥様は同じ有名大学にちゃんと受験して入学した才女であり、帰国子女でもある奥様は英語が完璧でそれはそれは有能な方なのだそうです。
「どうしてこんな俺が、そんな才女と結婚できたかと言えば」、Nさん曰く、何でも奥様は中学時代の3年間、オーストラリアで過ごしたので英語はできるけれど、その一方で、
「どうしてこんな俺が、そんな才女と結婚できたかと言えば」、Nさん曰く、何でも奥様は中学時代の3年間、オーストラリアで過ごしたので英語はできるけれど、その一方で、
帰国してからは「自分は日本語が下手なんだ」という事がコンプレックスとなってしまい、電話連絡網などでメッセージが回って来た時などは、言う事を書いて、何度も練習してからでないと、怖くて受話器も握れない程だったのだという事です。
そんな奥さんから言わせれば、時には司会をしたりして大衆の前で堂々と話をしたり笑わせたりできるNさんの能力は、それはもう「尊敬の対象以外の何物でもない」という事になるのだとか。
子供にとって「人と違う事」は、それ自体がストレスなものです。子供の世界は残酷なものですから「みんなと同じ」でなければ必ず指摘の対象となります。
子供にとって「人と違う事」は、それ自体がストレスなものです。子供の世界は残酷なものですから「みんなと同じ」でなければ必ず指摘の対象となります。
日本で普通に学校に通っていたって、「苛め」やお友達との人間関係を苦に、登校拒否や自殺をする子供もいるものです。
「言葉が下手」である事は「残虐な子供の世界」の中で生き抜いて行くためには相当に不利な条件となります。その中で何とか生き抜ける子供もいれば、中には生涯抱える傷を負う子供もいます。
「子供だから大丈夫。そのうち慣れるわよ。」と、人は簡単に言うものです。でも「そのうち」の長さは子供によって異なり、それが短い子供もいれば、長くかかる子供も、中にはそれが永遠に来ない子供もいて、時には「それを諦める勇気」を必要とする事もあるものです。
「子供だから大丈夫。そのうち慣れるわよ。」と、人は簡単に言うものです。でも「そのうち」の長さは子供によって異なり、それが短い子供もいれば、長くかかる子供も、中にはそれが永遠に来ない子供もいて、時には「それを諦める勇気」を必要とする事もあるものです。
その「見極め」の基準は、その子にとって「バイリンガルになる事」による「メリットと弊害のどちらが大きいのか」という事なのではないでしょうか。
それは「人生の挫折」ではなく「子供が幸福になるための選択」に過ぎません。結局、「最終的に目指すべき事」は、「子供が幸せな人生を送る事」であった事を、親が忘れてしまわないように したいものです。
2005年 筆:滝つぼ
それは「人生の挫折」ではなく「子供が幸福になるための選択」に過ぎません。結局、「最終的に目指すべき事」は、「子供が幸せな人生を送る事」であった事を、親が忘れてしまわないように したいものです。
2005年 筆:滝つぼ
6セミリンの育て方
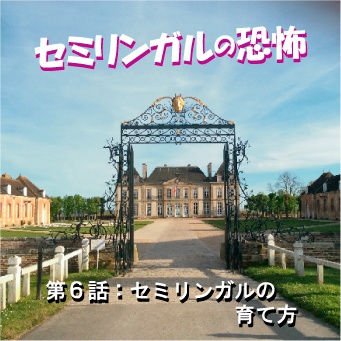
第6話・セミリンガルの育て方
長男が2歳半になった頃、当時イギリスに住んでいた私は「子供をバイリンガルに育てたい」という私の理想に反し、長男の言葉が思うように発達していない事に悩んでいました。
長男を英語と日本語の両方で育てて来た結果、長男は言葉が混ざってしまい、どちらの言葉も発達が未熟で、年齢相応の母国語を持たない「セミリンガル」になってしまっていたのです。
子供が言語を習得する時には、何度も言葉を聞き続ける中で、子供なりにその「言語パターン」を見出し、ルールを把握する事によって言語を習得して行くものです。
その過程において、まったくルールの異なる2つの言語を同時進行させようとすれば、子供はその言語パターンを把握する事ができず、頭の中が支離滅裂となってしまいます。
とは言え、まだ母国語が確立していない幼児に2つの言葉を覚えさせる事は、まったく不可能であるか、、と言えば、実際には、そうとは限らないものです。
とは言え、まだ母国語が確立していない幼児に2つの言葉を覚えさせる事は、まったく不可能であるか、、と言えば、実際には、そうとは限らないものです。
母親は日本語だけで話して父親は英語だけで話すとか、家庭内では日本語だけで話して外では英語で話すなど、環境に応じて言葉をきちんと使い分ければ、子供の方でも「人によって、話す言葉が違う事」に気づき、「2つの違う言語が存在するのだ」という事を理解しやすいので、2つの言葉も比較的スムーズに導入できるのだという事です。
それなら何故、うちの長男は言葉が混ざってしまったのかと言えば、それは「私が2つの言葉を混ぜて話しかけていたから」に他なりません。
私は長男を産んだ後、身体を壊してしまって家事や育児をこなすだけの体力がなくなってしまったので、夫の両親がしばらく手伝いに来てくれた後は、ドイツ人のオーペアー(若い住み込みのお手伝いさん)を雇っていました。
それなら何故、うちの長男は言葉が混ざってしまったのかと言えば、それは「私が2つの言葉を混ぜて話しかけていたから」に他なりません。
私は長男を産んだ後、身体を壊してしまって家事や育児をこなすだけの体力がなくなってしまったので、夫の両親がしばらく手伝いに来てくれた後は、ドイツ人のオーペアー(若い住み込みのお手伝いさん)を雇っていました。
お陰で我が家の主流言語は完全に英語となり、また、当時は周りに日本人の友人もまったくいない環境だった事も重なって、私以外のすべての人が英語を話す環境の中で、私が「子供に日本語だけを話しかけ通す」だけの勇気は、当時の私には持てませんでした。
だから私はその時の状況に応じて、時には日本語で、時には英語で、時にはその両方でと、子供に話しかける言葉を臨機応変に変えていたのです。そして、無知だった私はそんな自分の事を「子供に両方の言葉を教えるいいお母さん」だと思っていました。
海外で初めての出産、育児をし、身体も壊してしまったと同時に自信も失っていた私は、近くに親しい日本人の友人もなく、バイリンガルの育て方に対する正しい知識も正しいアドバイスを与えてくれる人もいない環境の中で、「子供に良かれ」と思って、ただ闇雲に子供に2つの言語を与えていました。
今、考れえばどうしてあんな事をしていたのか、自分でも理解に苦しいのですが、当時の私は「これが子供のためにしてやれる最善の方法」と信じて、「子供をセミリンガルにするための努力」を一生懸命にしていたのでした。
2005年 筆:滝つぼ
だから私はその時の状況に応じて、時には日本語で、時には英語で、時にはその両方でと、子供に話しかける言葉を臨機応変に変えていたのです。そして、無知だった私はそんな自分の事を「子供に両方の言葉を教えるいいお母さん」だと思っていました。
海外で初めての出産、育児をし、身体も壊してしまったと同時に自信も失っていた私は、近くに親しい日本人の友人もなく、バイリンガルの育て方に対する正しい知識も正しいアドバイスを与えてくれる人もいない環境の中で、「子供に良かれ」と思って、ただ闇雲に子供に2つの言語を与えていました。
今、考れえばどうしてあんな事をしていたのか、自分でも理解に苦しいのですが、当時の私は「これが子供のためにしてやれる最善の方法」と信じて、「子供をセミリンガルにするための努力」を一生懸命にしていたのでした。
2005年 筆:滝つぼ
7セミからバイリへ
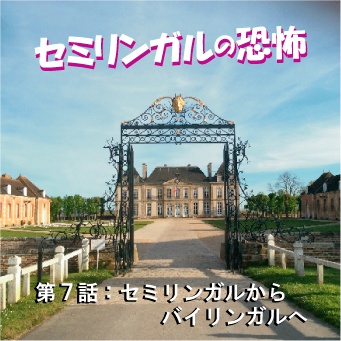
第7話.セミリンガルからバイリンガルへ
私達は当時イギリスに住んでいたのですが、長男が2歳半になった頃、生まれつき穏やかな性格だった長男が、何かにつけて「ムニャムニャッ」とわけのわからない事を言ったかと思うと、グワッとのけぞって癇癪を起こす、という行動を頻繁にするようになっていました。
これは長男の英語と日本語が混ざってしまって、どちらの言葉も発達が未熟で自分の意思を上手に伝えられないための苛々である事に気づいた私はその日から長男に英語で話しかける事にしました。
ちょうど幼稚園にも行くようになっていたタイミングも重なり、英語だけに絞った途端、長男の英語はメキメキと上達し、「自分の意思を伝達する手段」を確保できた長男は苛々して癇癪を起こす事も次第になくなっていきました。
こうして「子供に英語で話かけよう」と決意した日から、私は一貫して子供には英語だけで話しかけていたにも関わらず、やがて気がつけば驚いた事に、長男の日本語が、英語の上達の後を追うように比例して上達していったのです。
この不可解な現象を私なりに分析すれば、長男の言葉を英語だけに絞った事によって長男の母国語が確立し、それに伴って長男の知能も、言語に対する適応能力も高まった結果、長男は「世の中には英語と日本語というまったく別々の言語が存在するのだ」という事をはっきりと認識できたため、長男は英語だけでなく日本語も上達したのだ、と私自身は解釈しています。
この時私は、子供の知能や性格の正常な発達のためには「母国語を発達させる事」がどんなに重要な事であるかを思い知ったのでした。
やがて長男はいつの間にかイギリス人のお友達とは英語で、日本人のお友達とは日本語で、と言葉を使い分ける事ができるようになり、「セミリンガル」から「バイリンガル」へと次第に変化して行きました。
正直、私の下手な英語で子供に話しかけるのは自分にも相当な抵抗があったし、私にとってそれは「最高の屈辱」でもありました。
これは長男の英語と日本語が混ざってしまって、どちらの言葉も発達が未熟で自分の意思を上手に伝えられないための苛々である事に気づいた私はその日から長男に英語で話しかける事にしました。
ちょうど幼稚園にも行くようになっていたタイミングも重なり、英語だけに絞った途端、長男の英語はメキメキと上達し、「自分の意思を伝達する手段」を確保できた長男は苛々して癇癪を起こす事も次第になくなっていきました。
こうして「子供に英語で話かけよう」と決意した日から、私は一貫して子供には英語だけで話しかけていたにも関わらず、やがて気がつけば驚いた事に、長男の日本語が、英語の上達の後を追うように比例して上達していったのです。
この不可解な現象を私なりに分析すれば、長男の言葉を英語だけに絞った事によって長男の母国語が確立し、それに伴って長男の知能も、言語に対する適応能力も高まった結果、長男は「世の中には英語と日本語というまったく別々の言語が存在するのだ」という事をはっきりと認識できたため、長男は英語だけでなく日本語も上達したのだ、と私自身は解釈しています。
この時私は、子供の知能や性格の正常な発達のためには「母国語を発達させる事」がどんなに重要な事であるかを思い知ったのでした。
やがて長男はいつの間にかイギリス人のお友達とは英語で、日本人のお友達とは日本語で、と言葉を使い分ける事ができるようになり、「セミリンガル」から「バイリンガル」へと次第に変化して行きました。
正直、私の下手な英語で子供に話しかけるのは自分にも相当な抵抗があったし、私にとってそれは「最高の屈辱」でもありました。
でも「今のこの子にとって本当に大切な事は何であるか」だけに問題を絞ってよくよく突き詰めて考えた時、「イギリスに住んでイギリス社会に生きているこの子にとって、英語ができるようになる事は何よりも必要不可欠な事であり、逆に日本語なんて、できた方がいい程度の事に過ぎない。
どうしてもそれにこだわっていたのは、他でもない私自身の母親としてのプライドのためだ。」という心の奥底の自分の本心に気が付いたのです。
こうして「子供のため」という大義名分の陰に隠れていた自分自身の「見栄と執着」の存在に気がついた時、私は「自分の子供に英語で話しかける勇気」を持つ事ができたのでした。
どこまでも根性を貫くのも大切な事かも知れません。でも、うまく行っていないと気づいた時は潔く諦めて、ちょっと方向を変えてみると、時にはそれが「幸福への近道」だったりする事もあるものだと思います。
こうして「子供のため」という大義名分の陰に隠れていた自分自身の「見栄と執着」の存在に気がついた時、私は「自分の子供に英語で話しかける勇気」を持つ事ができたのでした。
どこまでも根性を貫くのも大切な事かも知れません。でも、うまく行っていないと気づいた時は潔く諦めて、ちょっと方向を変えてみると、時にはそれが「幸福への近道」だったりする事もあるものだと思います。
2005年 筆:滝つぼ
8日本語だけで育て

第8話.日本語だけで育てた下二人
これは私の個人的で限られた経験から得た持論ですが、英語という言葉は国際語になっただけの事はあって、構造が簡単で習得が容易なので、英語と日本語を同じだけ子供に与えただけでは、英語の方が必ず勝つものです。
だから英語の環境にいても子供に日本語を習得させたいと本気で思う場合は、相当量の日本語を子供に与える必要があると思います。
長男の時は産後に健康を害したのと同時に自信も失っていた私も、次男を生む頃までにはすっかり自分らしさを取り戻していました。車の運転もできるようになって行動範囲も広がり、日本人の集まる公文教室や読み聞かせグループなどに積極的に参加したり、情報誌を発行したり等して、地元では駐在員の奥様方から何かと頼りにされる存在となっていました。
こうして日本人のお友達にも囲まれ、日本語の本やビデオや童謡のテープなど、日本語の教材も豊富になり、次男の時には一転して子供を日本語だけで育てるには申し分のない環境となりました。
長男で苦い経験をした私は、次男の事は日本語だけで育てる事にしました。日本人のお友達だけと遊ばせ、テレビもビデオも殆ど日本語だけを見せ、日本語の本を読み聞かせて、と一貫して日本語だけで育てました。約2歳違いで生まれた3人目の末娘も同様に育てたので、下二人の母国語は日本語となりました。
とは言え、イギリスに住んでいる以上、英語が生活の中に入って来ないわけには行きません。でも、次男は生まれつき言葉が得意な様子で、長男のように言葉が混ざって混乱する事もなく、比較的容易に2つの言葉をきちんと切り替え、どちらの言葉も順調に発達していきました。
長男の時の苦労が嘘のように、次男の言語教育は簡単でした。私はつくづく「長男が先に生まれてくれて良かった」と思います。もし、次男のように簡単に言語を習得できる子供を育てた後で、長男が生まれたらどうだったでしょうか。
「上の子はこの方法でちゃんとできた」という経験から、自分のやり方に確信を持ち、「できるようにならない次男」に対して、どう対処していいのか理解できなかっただろうと思います。その挙句、「あの子はちょっと頭がおかしいのよ」と、私も言っていたかも知れません。
「兄弟を同じように育てる」のは不可能な事です。親も子育ての経験を通して子供と一緒に成長し、長男を育てた時よりも次男の時の方が「より良い親」になっている反面、ゆとりも出て来て「手抜き」も始まるものです。
言語教育では苦労した長男でしたが、彼は生まれつき性格が穏やかで、初めて子育てするにはとてもラクな子供でした。一方、次男は生まれつき気性が激しく、いつも怪鳥獣のようにギーギーと泣き喚き、彼には本当に苦労させられました。
「子供によって能力もニーズも違うのだから、その子に合わせて個別に対応するべきである」というのが、3人の子供達を育てて来た私の持論です。
2005年 筆:滝つぼ
「兄弟を同じように育てる」のは不可能な事です。親も子育ての経験を通して子供と一緒に成長し、長男を育てた時よりも次男の時の方が「より良い親」になっている反面、ゆとりも出て来て「手抜き」も始まるものです。
言語教育では苦労した長男でしたが、彼は生まれつき性格が穏やかで、初めて子育てするにはとてもラクな子供でした。一方、次男は生まれつき気性が激しく、いつも怪鳥獣のようにギーギーと泣き喚き、彼には本当に苦労させられました。
「子供によって能力もニーズも違うのだから、その子に合わせて個別に対応するべきである」というのが、3人の子供達を育てて来た私の持論です。
2005年 筆:滝つぼ
9イギリスの教育レ
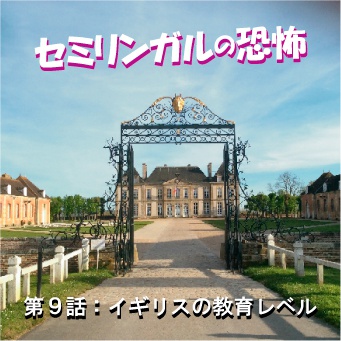
第9話.イギリスの教育レベル
寄宿舎育ちの夫の話では「イギリスの公立学校の教育レベルは低い」という事だったので、長男の事は3歳から私立の学校に入れる事にしました。
ところが「子供一人の教育費で、一軒づつ家が建つ」と言われる程、学費は高いくせに、レベルは大した事がない私立校に嫌気が刺した私達は、私が3人目を妊娠したのをきっかけに、長男を公立校に転校させる事にしました。
幸い、私達の住んでいた地域は良い環境でしたし、長男の学校は新設校で、先生達も父兄達も教育熱心で、学校は活気に満ち溢れており、教育委員会の視察団からも高い評価を受けたとかで、私は本当に運が良かったと喜んでいました。
私が私立校から公立校へ変えた事による絶対的な落差を感じたのは、送り迎えの時に学校周辺の道路にずらっと駐車された車の違いを見た時だけでした。
私立校の時は家にスイミングプールもあるような大邸宅の子供とも同級生だった長男も、今度は生活保護を受けたりしている家庭の子供とも交わるようになったのですが、公立校育ちの私は、「それも良い経験だ」と思っていました。
ところが長男が公立校に通うようになってしばらく経つと、夫が長男の発音を頻繁に直すようになって行ったのです。そして家では「使ってはいけない」と教えているトイレットやデザートなどの言葉も長男は口にするようになって行きました。
そしてある時、学芸会を見に行って学校の様子を見た夫は「一刻も早く学校を変えなければ」と青くなってしまいました。「このままでは長男にアクセントが身に付いてしまう」と言うのです。
その人の英語の発音を聞けば、教育レベルも家庭環境も殆どわかってしまうと言われる程、イギリスの階級社会は歴然としています。でも外国人である私の英語力のレベルでは、そんな事まではわからなかったのです。
幾ら夫が必死で発音を直しても、学校にいる時間の方が長い子供の発音は、どんどん変化して行きました。でも私には、夫が「そうじゃなくてこうだ」と言って子供に直させているどちらの発音も殆ど同じに聞こえるので、何の役にも立つ事ができません。
思案の末、夫が自宅勤務のビジネスに転職したのをきっかけに、私達は「公立校のレベルが高い」と言われているフランスに移住する事にしました。
正直、私はやっと住み慣れたイギリスを離れて言葉のできない国で生活するのは嫌でしたし、言葉の苦手な長男のフランス語への適応能力の事も心配でした。それに長男は当時既に8歳近くなっていて勉強も難しくなり始めており、母国語を変えさせるには遅すぎる年齢かも知れない事が懸念されました。
しかし、学校でフランス語を習得し、家では夫から正しい発音の英語を習得する方が、こうしてアクセントが身についてしまうよりは、ずっと子供達の将来のためになると主張する夫の意見に、外国人の私は従うしかありませんでした。
2005年 筆:滝つぼ
11混ざらない英と仏
11. 混ざらない英語とフランス語
英国で生活していた頃、日本人家庭のお子さん達は皆、現地校に通い初めてしばらくすると、兄弟同士では英語で話をするようになって行ったものでした。これは子供達の英語力が発達するにつれ、英語で話す方がラクになるので、英語の通じる兄弟同士では「自分にとってラクな言語」が出て来るからです。
うちの子供達はフランスに暮らすようになって6年以上経つのですが、私に聞かれたくない秘密の話を兄弟同士でする時以外は、我が家では兄弟喧嘩もすべて英語です。
子供達に「どちらの言葉の方がラクなのか」を聞いてみると、「自分達にとっては、どちらもそうは変わりないが、英語の方が構造が単純なので、英語を使うのはラクだ」という事でした。
フランス語には男性名詞だの女性名詞だのがあり、動詞の活用変換も複雑でいちいち変形し、それらを全部覚えていかなければなりません。もちろん英語にも基本形以外の活用法を取る動詞もありますが、全体としてはやはり基本的構造が単純ですし、多少間違えても通じる「いい加減さ」が、英語を国際語にした所以であると思います。
だから私としては「英語とフランス語の場合は英語の方が優勢になるのだ」と、単純に思っていました。ところが先日、たまたま電車で隣りに乗り合わせた親子の様子を見ていて、私の考えも少し変わりました。
それは12歳位の女の子と10才位の男の子を連れたイギリス人の母親で、私達と同じように元々イギリスに住んでいたけれど、何年か前にフランスに移住して来たらしかったようでした。
子供達は電車の中で学校の宿題をやらされている様子でした。最初、二人は姉弟同士で英語で話していたのですが、それがいつの間かフランス語になり、しばらくするとまた英語に戻りという感じで、フランス語と英語を行ったり来たりして会話をしていました。
すると母親も同じように、子供達に英語で話していたかと思うといつの間にフランス語になりと、同じように行ったり来たり。この家庭では二つの言葉を完全に混ぜて使っているようでした。
私はフランス語がまったくできないし、夫も相当下手なので、我が家の子供達は私達と話す時は絶対にフランス語を混ぜたりはしなません。だから私にとってこの親子の光景はちょっと驚きでした。
しかもこの母親はフランス語が相当できるだけあって大変教育熱心な様子で、子供達に両方の言葉を習得させるため、彼女はわざとそうしている様子でした。
この時、私は黙っていたのですが、心の中では「我が家では親達がフランス語ができるようにならなかったお陰で、うちの子供達は二つの言語を混ぜないで発達する事ができたのだという事に、今、初めて気付いたわ」と思っていました。
この二人の子供達はこれから先、どんな風に成長して行く事になるのでしょうか。私にはそれを知るすべもありません。
2005年 筆:滝つぼ
うちの子供達はフランスに暮らすようになって6年以上経つのですが、私に聞かれたくない秘密の話を兄弟同士でする時以外は、我が家では兄弟喧嘩もすべて英語です。
子供達に「どちらの言葉の方がラクなのか」を聞いてみると、「自分達にとっては、どちらもそうは変わりないが、英語の方が構造が単純なので、英語を使うのはラクだ」という事でした。
フランス語には男性名詞だの女性名詞だのがあり、動詞の活用変換も複雑でいちいち変形し、それらを全部覚えていかなければなりません。もちろん英語にも基本形以外の活用法を取る動詞もありますが、全体としてはやはり基本的構造が単純ですし、多少間違えても通じる「いい加減さ」が、英語を国際語にした所以であると思います。
だから私としては「英語とフランス語の場合は英語の方が優勢になるのだ」と、単純に思っていました。ところが先日、たまたま電車で隣りに乗り合わせた親子の様子を見ていて、私の考えも少し変わりました。
それは12歳位の女の子と10才位の男の子を連れたイギリス人の母親で、私達と同じように元々イギリスに住んでいたけれど、何年か前にフランスに移住して来たらしかったようでした。
子供達は電車の中で学校の宿題をやらされている様子でした。最初、二人は姉弟同士で英語で話していたのですが、それがいつの間かフランス語になり、しばらくするとまた英語に戻りという感じで、フランス語と英語を行ったり来たりして会話をしていました。
すると母親も同じように、子供達に英語で話していたかと思うといつの間にフランス語になりと、同じように行ったり来たり。この家庭では二つの言葉を完全に混ぜて使っているようでした。
私はフランス語がまったくできないし、夫も相当下手なので、我が家の子供達は私達と話す時は絶対にフランス語を混ぜたりはしなません。だから私にとってこの親子の光景はちょっと驚きでした。
しかもこの母親はフランス語が相当できるだけあって大変教育熱心な様子で、子供達に両方の言葉を習得させるため、彼女はわざとそうしている様子でした。
この時、私は黙っていたのですが、心の中では「我が家では親達がフランス語ができるようにならなかったお陰で、うちの子供達は二つの言語を混ぜないで発達する事ができたのだという事に、今、初めて気付いたわ」と思っていました。
この二人の子供達はこれから先、どんな風に成長して行く事になるのでしょうか。私にはそれを知るすべもありません。
2005年 筆:滝つぼ
12お前はなに人だ?
12. お前はなに人なんだ?
「シントク、シントク」
長男が中学に入学したての頃、長男は意地悪な上級生達から「シントク、シントク!」と言われて苛められました。「シントク」とはフランス語で「アホな中国人」という意味なのだそうです。
それを聞いて私達は「そんな事を言われて黙っていてはいけない。僕はシントクじゃなくて、ジャプトクだぞ!と言い返しなさい。」と言いました。
フランス人にとっては日本人も中国人も殆ど区別は付きません。周りの子供達の中には長男は「フランス人と中国人のハーフだ」と勝手に思い込んでいる子も多いようです。
長男の顔を見れば「純粋なフランス人ではない」事は理解できても、その上「フランス人でもない」という点が、周りの子供達にとっては「どうも腑に落ちない」ようです。
「じゃあ、お前は半分は日本人で、半分はイギリス人で、半分はフランス人なのか?」と、真面目に聞く子もいたとか。これには長男も飽きれてしまい、「それじゃ、足し算が合わないだろ!」と言ったという事でした。
それを聞いて私達は「そんな事を言われて黙っていてはいけない。僕はシントクじゃなくて、ジャプトクだぞ!と言い返しなさい。」と言いました。
フランス人にとっては日本人も中国人も殆ど区別は付きません。周りの子供達の中には長男は「フランス人と中国人のハーフだ」と勝手に思い込んでいる子も多いようです。
長男の顔を見れば「純粋なフランス人ではない」事は理解できても、その上「フランス人でもない」という点が、周りの子供達にとっては「どうも腑に落ちない」ようです。
「じゃあ、お前は半分は日本人で、半分はイギリス人で、半分はフランス人なのか?」と、真面目に聞く子もいたとか。これには長男も飽きれてしまい、「それじゃ、足し算が合わないだろ!」と言ったという事でした。
「僕はどうして半分なの?」
長男が4歳の頃、長男は「自分の母親が日本人である事」がとても嫌だったようでした。それは「母親である私の事が嫌い」というわけではなく、「みんなと同じでない事がイヤ」という気持ちだったようでした。
こうして長男はとても早い時期から、「僕はどうして半分なんだろう」という事を悩んだようですが、今では「変えようのない事実として受け入れた」のだそうで、「女の子にモテルからいい」程度に思っているそうです。
一方、下の二人の場合は、周囲も長男を知る事で「異質なハーフの存在」に慣れてしまうせいなのか、本人達の性格のせいなのか、とにかくあまり深く悩んだりはしなかった様子です。
「郷に入っては郷に従え」
うちの子供達は小さい頃から「異文化に適応する環境」に慣れさせられて来たせいか、「その環境の雰囲気をいち早く察知して、その中に自分を同化させるワザ」を習得している様子です。
最近では「お母さん、ここはフランスなんだよ。フランスではこういう風にするんだから、しょうがないでしょ!」と私の方が子供によく説教をされます。
子供達にはそれぞれ仲良しなお友達がいて、フランスでのソーシャルライフは今のところ充実している様子です。周囲の子供達にとって、うちの子供達は完全に「自分達の仲間」と感じてくれているようです。
日本での体験入学
2年前、子供達が6年、3年、1年生の時、一週間だけですが、日本の小学校で体験入学をしました。子供達は初めて歩いて集団登校をしたり、立って皆でお辞儀をしたり、給食当番や掃除当番など、「日本語」だけではなく、様々な「異文化体験」をしました。
一週間だけでしたが、子供達にとってとてもよい体験だったようで、帰国後フランスでも日本の学校での体験談をクラスで発表したのだという事です。
他所の家のルールに従う
「異文化の中で協調していく事」は、「他所の家にお邪魔した時のルール」のようなもの。自分の家では普段こうしていた事でも、他所の家ではその家のルールに従うのが「マナー」です。
フランスにはフランスなりの、イギリスにはイギリスなりのマナーやルールがあり、それぞれの国で「こうしてはいけない事」や「こうしなきゃいけない事」が存在する事を知る事によって「国が違えば、当然、別の事で同じようなルールがあるのだ」という事が簡単に理解できるようになります。
こうしたルールを理解して自分を同化させる事は「子供の個性を潰し子供を萎縮させる事」ではなく「人間としてのマナーを教える事」だと思います。
お国は違っても「マナーの基本」には共通点が多く、要は「相手に対する敬意の念」。その基本さえ理解していれば、国によって違うのはその「表現方法」だけですから、それを理解するように努力していれば、周囲も受け入れてくれるものだと思います。逆に、その基本がない人は、国を変えても、やはり同じである事が多いようです。
2005年 筆:滝つぼ
13相乗効果を生むヨ
13.相乗効果を生むヨーロッパ言語
5ヶ国語を話すご主人
ベルギー人と結婚した私の親友のご主人は、フランダース語(オランダ語)、フランス語、ドイツ語、英語、日本語の5ヶ国語を操る語学の天才。
彼の話では「ヨーロッパの言語は語源が同じで似ている言葉も多く、習得言語の数が増えてくると、かえって簡単に別の言語を覚える事ができるようになって行くのだ」との事。その意味では彼にとって「日本語を習得する事が最も大変だった」という事です。
もちろん本人の素質や努力などもあるでしょうが、語学間の距離の近い言語を習得する方が、遠いものを習得するよりも容易である事は事実なようです。
彼の話では「ヨーロッパの言語は語源が同じで似ている言葉も多く、習得言語の数が増えてくると、かえって簡単に別の言語を覚える事ができるようになって行くのだ」との事。その意味では彼にとって「日本語を習得する事が最も大変だった」という事です。
もちろん本人の素質や努力などもあるでしょうが、語学間の距離の近い言語を習得する方が、遠いものを習得するよりも容易である事は事実なようです。
フレンチ英語
私達がフランスに来てから約7年。家では英語を話す子供達ですが、学校教育はすべてフランス語なので、フランス語で初めて習う言葉も多く、子供達は「英語では何て言うのか知らない言葉も沢山ある」という状態です。
そんな時、子供達はフランス語から推察した「英語の造語」を用いて表現しようとします。英語とフランス語では同じスペルの単語をフランス語読みから英語読みに変えるだけの単語も多いので、それで偶然正解である場合もあるのですが、はずれる事もあり、子供達が突然「何それ?」という謎の言語を言い出して大笑いとなったりします。
例えば、末娘は「パニッシュメント」という言葉を忘れてしまい、「パニッション」と言いました。これはフランス語では「パニシオン:罰」という言葉を英語読みにしたものです。
フランス語をそのまま英語にした言葉には「小さな子供は使わない言葉」という単語も多く、普通なら長男の年齢では使わないような難しい言葉を長男がよく知っていて、夫が驚く事が多くある、という事です。
そういった理由からも、フランス語を身につける事は英国人にとっては教養を高めるのに重要な役割を果たす事になるわけです。
日本人のバイリンガル
このようにヨーロッパ人にとって「バイリンガルになる事」はかえって母国語の発達に繋がる場合すらあるため、「絶対に良い事」として認識されているようです。
しかし日本語を母国語とする私達日本人は、日本人であるが故に生じる「セミリンガルの弊害」の実態を認識し、子供達を正しい方向に導いて行く必要があります。
それを痛感した私としては、日本人の子供達に「間違った努力」をさせないよう、少しでも多くの人達にその事実を伝えていきたいと思っています。
2005年 筆:滝つぼ
14難しい日本語の保
14.難しい日本語の保持
落ちて行った日本語力
英国からフランスに移転した時、「今の子供達にとってはフランス語を習得する事が最も大切な事だ」と思った私は、「子供達の日本語を維持する事への執着心」を捨てる事にしました。
自宅勤務になった夫がいつも家にいたので家庭の言語も英語が主体となり、また、パリまで3時間の田舎、日本人など誰もいない環境にもなりました。
そして極めつけは、私が単身赴任で家を留守がちにした事です。こうして日本語を使う必要も機会も激減してしまい、子供達の日本語力は坂道を転げるように落ちていってしまいました。
母親の責任
専業主婦だった頃は「私がフルで子供を見ているのに、子供は日本語ができるようにならない」というのは「屈辱」以外の何物でもありませんでした。
そして働くようになれば「私が一緒にいないから子供達の日本語が落ちたのだ」という思いはとかく「最悪感に苛まれる元」となるものです。
確かに親が一生懸命に手をかければ、子供の能力はある程度それで左右されるので、「子供の出来、不出来」は母親の責任に負うところが多いのは事実だと思います。
だからこそ、それが思うようにうまく行かない場合はとかく母親である自分が「裁かれる」ような気分にさせられるものです。
東大に行きたい
先日、長男が突然「僕、ト-ダイに行きたい」と言い出しました。「ト-ダイ」とはあの「東大」の事なのだそうで、東大入試を目指す予備校生を主人公にした「ラブヒナ」とかいう漫画の影響なのだそうです。
子供達にとっては「ポケモン」や「ドラゴンボール」などが「日本発信」である事などが、回りの子供達に対しては「自慢」の材料であるようで、子供達の日本語はアニメで聞いた言葉から増えている、というのが現状です。
ダメなお母さん
専業主婦をしている時ですら難しかった子供の日本語の保持。今では殆ど家で仕事をしている私ですが、働きながらの子育てはどうしても「手抜き」となり、子供の日本語保持は至難の業。
「完璧な母親」でいようとすると、子供を叱る機会も増えるものです。私が「教育ママ」だった頃は確かに子供達の成績は良かったですが、子供達は私を怖がっていたものでした。それが今では「ダメなお母さんでごめんね~」と子供達に謝りながら適当に暮らす毎日。子供達の成績は落ちましたが、逆に笑顔は多くなりました。
2005年 筆:滝つぼ
15言語と性格
15.言語と性格
ウィット(Wit)
先日、長男があまりに酷い成績を取って来たのでプッツン切れた私は「こんなんで、あんたの将来は一体どうなるの!」と長男を怒鳴りつけました。
すると長男はニッコリと微笑み、「でもね、お母さん。アインシュタインも学校の成績は悪かったそうだから、そんなに悲観する事もないよ」と言って私を慰めてくれました。
それを聞いて大笑いしてしまった私は、もうそれ以上、お説教を続ける事ができなくなってしまいました。
こうした「とんちの利いた切り返し」の事を英語ではウィットと言います。イギリスではこのウィットができる事が大変重要で、私の個人的な考えでは、外国人が英国社会に溶け込むためには「完璧な発音」を習得する事よりも、むしろ「ウィットができる事」の方がもっと重要な事であると思います。
すると長男はニッコリと微笑み、「でもね、お母さん。アインシュタインも学校の成績は悪かったそうだから、そんなに悲観する事もないよ」と言って私を慰めてくれました。
それを聞いて大笑いしてしまった私は、もうそれ以上、お説教を続ける事ができなくなってしまいました。
こうした「とんちの利いた切り返し」の事を英語ではウィットと言います。イギリスではこのウィットができる事が大変重要で、私の個人的な考えでは、外国人が英国社会に溶け込むためには「完璧な発音」を習得する事よりも、むしろ「ウィットができる事」の方がもっと重要な事であると思います。
「使用言語」と「性格」
長男は子供ながらこのウィットが大変上手で、思いがけない事を言い出していつも笑わせてくれます。
「お兄ちゃんは学校でも皆から面白いって言われるでしょ?」と長男に聞いたところ、「フランス語を話している時の僕はもっとシャイ(恥ずかしがり)だよ。」と言いました。
特にフランス語で話す場合は友人同士の会話が殆どで大人と話す機会も少ないし、フラン人のユーモアのセンスはイギリス人とは違うので、彼らの事をどうやって笑わせたら良いのか、わからないのだとか。
逆に、英語を話す場合は夫や私など、相手が大人である場合が殆どなので、ウイットを使い易いという事です。
因みに、長男の日本語での口癖は「だいじょぶ、だいじょぶ。あれっ!・・・・・まあ、いっか~!」
どうやら長男の性格はフランス語では「消極的」、英語では「ユーモア溢れて哲学的」、日本語では「楽天的」と、それぞれ話す言語や状況に応じて変化しているようです。
特にフランス語で話す場合は友人同士の会話が殆どで大人と話す機会も少ないし、フラン人のユーモアのセンスはイギリス人とは違うので、彼らの事をどうやって笑わせたら良いのか、わからないのだとか。
逆に、英語を話す場合は夫や私など、相手が大人である場合が殆どなので、ウイットを使い易いという事です。
因みに、長男の日本語での口癖は「だいじょぶ、だいじょぶ。あれっ!・・・・・まあ、いっか~!」
どうやら長男の性格はフランス語では「消極的」、英語では「ユーモア溢れて哲学的」、日本語では「楽天的」と、それぞれ話す言語や状況に応じて変化しているようです。
「言語の自信度」と「性格」
この違いは長男にとっての「その言語に対する自信度」と関連があるように思います。
8歳直前にフランスに来た長男にとって「最も自信の持てる言葉」はやはり英語であり、どこかに一抹の不安が残る」のがフランス語であり、「どうせできないので開き直っている」のが日本語なのです。
「その言語に対する自信度がその言語を話す時の性格にも反映される」という事は、「自信のない状況に長いこと置かれれば、自信のない子供にさせてしまう可能性もある」とも言え、母国語を変えさせる事の危険性を改めて考えさせられる思いがしました。
2005年 筆:滝つぼ
「その言語に対する自信度がその言語を話す時の性格にも反映される」という事は、「自信のない状況に長いこと置かれれば、自信のない子供にさせてしまう可能性もある」とも言え、母国語を変えさせる事の危険性を改めて考えさせられる思いがしました。
2005年 筆:滝つぼ
16人種差別
16.人種差別
シントク、シントク
最近は次男も長男と同じ中学に通うようになり、次男もやはり長男の時と同じように「シントク、シントク」と、からかわれるのだと言いました。
長男はこれは既に経験済みの事なので、「あいつらは馬鹿だから、ほっとけばいい。そのうち飽きるから」と、次男にアドバイスをしていました。
長男に「学校では人種差別を受けているのか」と聞いたところ、「僕は今までの人生の中で、人種差別を受けたと感じた事は一度もない」と答えました。
「シントク」とは仏語で「アホな中国人」という意味なので、明らかに人種差別であると思うのですが、長男の理解では、何かしら「からかう材料」としてこれを使っているだけであって、「人種差別」ではないのだそうです。
長男はこれは既に経験済みの事なので、「あいつらは馬鹿だから、ほっとけばいい。そのうち飽きるから」と、次男にアドバイスをしていました。
長男に「学校では人種差別を受けているのか」と聞いたところ、「僕は今までの人生の中で、人種差別を受けたと感じた事は一度もない」と答えました。
「シントク」とは仏語で「アホな中国人」という意味なので、明らかに人種差別であると思うのですが、長男の理解では、何かしら「からかう材料」としてこれを使っているだけであって、「人種差別」ではないのだそうです。
「意地悪」か「人種差別」か
そう言えば私も、海外生活18年程になりますが、「人種差別を受けた」と感じた経験は殆どありません。
もちろん私も意地悪をされたり嫌な目に合った事は沢山ありますが、それを「人種差別だ」と思った事がないので、「差別を受けた事はない」と思っているだけで、本当は差別をされたのに、私が気がつかなかっただけだったのかも知れません。
確かに、他の人が差別を受けた話を聞いて初めて「じゃあ、あれも差別だったのか」と後から気が付いた、という事は何度かありました。
また人種差別!
私はよく夜行列車を利用するのですが、ある時、私はアラブ人系の人達と相室になりました。彼らは車掌にパスポートを取られた事を「人種差別を受けて不当に怪しまれたのだろう」と憶測していました。私が「何度もこの列車に乗っているが、身分証明書は必ず全員が取られる」と言ったら、やっと安心したようです。
つまり彼らは何事に対しても、まずは「人種差別か?」と疑う事が習慣となっているようでした。
またある時、列車の中で綺麗な黒人の女性が私の前の席に坐っていました。警察が来て彼女に「パスポートを見せろ」と言ってチェックすると、他の人達には見向きもせず去って行きました。
彼女が黒人だったからなのか、たまたま「ある黒人女性」を探していただけだったのかは知る由もありませんが、彼女は「人種差別をされた」と思ったであろう事が推察できました。
「人種差別」と取るか「単なる意地悪や偶然」と取るかは「受け取る側の取り方次第」であるとも言えます。少なくともうちの子供達は私と同様、人種差別をされても気がつかない「呑気タイプ」であるようです。
2005年 筆:滝つぼ
17日本への適応
17.日本への適応
帰国子女の受け入れ体制
海外での駐在生活を終えて帰国した子供達にとって、日本の学校生活に適応して行く事は重要な課題です。今月は「帰国特集」に因み、教育関係の方々から色々とアドバイスを頂きました。
特に帰国先が「保守的な地方」である場合は、帰国子女の前例も少ないため、学校側の受け入れ体制が経験不足で不充分であったり、周囲の子供達の反応が強い場合も予測されるという事です。
「いずれは帰国する駐在」の場合は、「帰国後の適応」の事も予め考慮して、学校を選択する事も大切なようです。海外の学校に慣れるために散々苦労し、やっと慣れた頃に帰国して、また同じ苦労をさせられる子供達の事を第一に考えた選択が必要だと言えるでしょう。
「損得勘定」に走る親の選択
「帰国子女」の枠に入れば、受験の際に有利になる等の理由から何年海外に滞在するか等を選択する人も多いかと思います。
もちろんこれは子供のためを思って、「できるだけ子供に有利になるように考慮してやりたい」という親心でそうするわけですが、子供によってそれが有効に働く場合と、意外にもかえってそれが子供には負担となって悪い結果を生む場合もあるのだそうです。
もちろん親も子供の意見を聞いた上で、本人も「そうしたい」と言っている場合でも、子供が親に気を使ってそう言っていただけで、必ずしも子供が本心を言っていない場合もあるので、その点への考慮も必要であるようです。
親が子供を守る
親も含めて無意識のうちに「外人」になっている場合もあるので、日本の生活に慣れるまでは、変な事をしないように気をつけて生活する事になります。
が、何をやっても「海外から帰って来た事をひけらかしている」と取られてしまうなど、色々と悪い条件が重なってしまって子供が「イジメ」を受ける事になった時、学校や先生の対応も大切ですが、一番大事なのは「親が子供を守る事」なのではないかと思います。
子供の世界は残酷なもので、イジメの対象は必ずと言っていい程、「弱い子」です。何か自分に自信が持てる事を伸ばしてやるのも一案ですし、護身術を兼ねて武道などを習わせるのも良いかも知れません。
うちの子供も学校で殴りかかられる事があったので、殴られたら殴り返すように教え、実際に殴られた時どう殴り返すかを夫が実演して家で練習させました。そんな強硬手段も時には有効に働くものです。
2005年 筆:滝つぼ
18コウモリとカメレ
18 コウモリとカメレオン
2000年の1月にイギリスからフランスに移住して丸8年。イギリス人の父と日本人の母を持つ子供たちの心の故郷は、ここノルマンディーなのです。 筆:滝つぼ
● 心の故郷ノルマンディー
三人の子供たちも16歳、12歳、10歳となり、それぞれに親しいお友達も近所にいて、ソーシャル・ライフも充実している様子です。近所の子供達は我が家が気に入っている様子で、次々と子供達が我が家に集まってきます。
私も夫もフランス語ができないし、私はいつも働いているしで、親達は子供達のお友達作りにはまったく貢献しませんでした。イギリスにいた頃は私もイギリス社会に溶け込もうと努力したものですが、フランスに来てからは、すっかり手抜きをしていたので、この人間関係は親の力を一切借りず子供達が自分達の力で築きあげたものです。
移住した当時7才だった長男はフランス語もまったくできない状態で学校に放り込まれ、母国語を変更させられ、自力でお友達を作って、この社会に溶け込んで、今の人間関係を確立させるまでに、並々ならぬ苦労をしたのだそうで、「もう、二度とあんな思いはしたくない」のだということです。
イギリス人でもなく、日本人でもなく、フランス人でもない子供達は、どこの社会にも完全には属する事ができません。でも、子供達は自分達の力でノルマンディーの人々に受け入れられ、このノルマンディーを「心の故郷」と感じているようです。
三人の子供たちも16歳、12歳、10歳となり、それぞれに親しいお友達も近所にいて、ソーシャル・ライフも充実している様子です。近所の子供達は我が家が気に入っている様子で、次々と子供達が我が家に集まってきます。
私も夫もフランス語ができないし、私はいつも働いているしで、親達は子供達のお友達作りにはまったく貢献しませんでした。イギリスにいた頃は私もイギリス社会に溶け込もうと努力したものですが、フランスに来てからは、すっかり手抜きをしていたので、この人間関係は親の力を一切借りず子供達が自分達の力で築きあげたものです。
移住した当時7才だった長男はフランス語もまったくできない状態で学校に放り込まれ、母国語を変更させられ、自力でお友達を作って、この社会に溶け込んで、今の人間関係を確立させるまでに、並々ならぬ苦労をしたのだそうで、「もう、二度とあんな思いはしたくない」のだということです。
イギリス人でもなく、日本人でもなく、フランス人でもない子供達は、どこの社会にも完全には属する事ができません。でも、子供達は自分達の力でノルマンディーの人々に受け入れられ、このノルマンディーを「心の故郷」と感じているようです。
●コウモリとカメレオン
私が思うに、異文化の中で生活する時、「コウモリ方式」を取る人と「カメレオン方式」を取る人と、2つに分かれるような気がします。
私が思うに、異文化の中で生活する時、「コウモリ方式」を取る人と「カメレオン方式」を取る人と、2つに分かれるような気がします。
「コウモリ方式」というのは自分の都合に合わせて方針がコロコロと変化する事。
「カメレオン方式」というのは、自分の置かれた環境に同化して、そこでの常識に従う事です。
方針が変化する点では両者は似ていますが、この2つは大きく異なります。例えばこんな例がありました。
以前、レストランで、ある事について日本人のお客様に「ここはドイツなんだから、ちゃんとドイツ式にやって下さい!」というご指摘を受けました。「そうでしたか。それは失礼しました」という事で、ドイツ式を取り入れました。
しかしその方は、あれほどドイツ式を主張したにも関わらず、レストランではチップを置くのがドイツ式ですが、それについては日本式に切り替えてチップは置いて行きませんでした。
つまり「コウモリ方式」というのは、自分の都合や利害に合わせて「いいとこ取り」をすることです。
以前、レストランで、ある事について日本人のお客様に「ここはドイツなんだから、ちゃんとドイツ式にやって下さい!」というご指摘を受けました。「そうでしたか。それは失礼しました」という事で、ドイツ式を取り入れました。
しかしその方は、あれほどドイツ式を主張したにも関わらず、レストランではチップを置くのがドイツ式ですが、それについては日本式に切り替えてチップは置いて行きませんでした。
つまり「コウモリ方式」というのは、自分の都合や利害に合わせて「いいとこ取り」をすることです。
一方「カメレオン方式」は、たとえそれが自分の元々の文化や常識とは異なり、自分にとっては不利だったり不都合だったりする事でも、潔くその環境のしきたりに従うやり方です。こういう生き方をすればたとえ外国人やよそ者であったとしても、その社会ではきちんと受け入れてもらえるものなのだと思います。
●カメレオンに徹した子供達
うちの子供達は小さい頃から「みんなと違う事」を強いらされて生きて来ました。イギリスでも日本でも片親は外国人。フランスでは両親ともが外国人。「みんなと違う事」は子供達にとっては「耐え難い苦痛」なのです。
そんな環境の中で周りから「なんだ、僕らと同じだね」と扱ってもらう事は、子供にとっては死活問題。自己防衛本能が働いて、瞬時にその環境ではどんな風に振舞うべきなのかをいち早く察し、その環境の中に同化して「皆と同じになる」事をうちの子供達は本能的に学び、身に着けたのだと思います。
イギリス人のお父さんと日本人のお母さん。こんな特殊な家庭でも周囲から「仲間はずれ」にされる事なく、自分達の幸せを自分達の手で勝ち取った子供達。フランス語もドイツ語もできるようにならず、日本人社会の中だけで生きている私としては、そんな子供達に我が子ながら、「アッパレ!」と、褒めてやりたい心境です。
うちの子供達は小さい頃から「みんなと違う事」を強いらされて生きて来ました。イギリスでも日本でも片親は外国人。フランスでは両親ともが外国人。「みんなと違う事」は子供達にとっては「耐え難い苦痛」なのです。
そんな環境の中で周りから「なんだ、僕らと同じだね」と扱ってもらう事は、子供にとっては死活問題。自己防衛本能が働いて、瞬時にその環境ではどんな風に振舞うべきなのかをいち早く察し、その環境の中に同化して「皆と同じになる」事をうちの子供達は本能的に学び、身に着けたのだと思います。
イギリス人のお父さんと日本人のお母さん。こんな特殊な家庭でも周囲から「仲間はずれ」にされる事なく、自分達の幸せを自分達の手で勝ち取った子供達。フランス語もドイツ語もできるようにならず、日本人社会の中だけで生きている私としては、そんな子供達に我が子ながら、「アッパレ!」と、褒めてやりたい心境です。
2008年・筆:滝つぼ
19 質問にお答えして
19 皆様からの質問にお答えして
シリーズで掲載している「セミリンガルの恐怖」。皆様からの反響も多く、色々な方々からご意見、ご質問などを頂き、ありがとうございます。
今回は「セミリンガル・スペシャル」として、皆様からのご意見等にお応えする視点から書きたいと思います。
今回は「セミリンガル・スペシャル」として、皆様からのご意見等にお応えする視点から書きたいと思います。
「他人の体験談」は「他人の体験」
「セミリンガルの恐怖」では私自身が自分の子育ての体験を通して発見した事や考えた事を書いています。これはあくまでも私とうちの子供達の個人的な体験です。
私の失敗談を読んで、「うちの子は大丈夫かしら?」と振り返る機会を持つのも時には良い事かも知れません。が、心配のあまり、バイリンガル教育を諦めてしまう必要はないと思います。
子供の能力は個人差が大きく、兄弟でもまったく違いますし、また、何歳で来て、何年いて、何歳で帰るのか等によっても大きく左右されるので、様々なケースが存在します。
大切なのは、「バイリンガル教育というのはとても大変な事なのだ」という事を自覚した上で、親が常にアンテナを立て、子供の様子を把握しておく事だと思います。
くれぐれも「こうすれば誰でもバイリンガルになれる!」式の自慢話を鵜呑みにして、「じゃあ、うちの子も!」とその気にならないで下さい。
「インターナショナル・スクール」のブームに踊らされない
語学は「伝染病」ではないので「子供をインターナショナル・スクールに入れさえすれば簡単にバイリンガルになれる」と思うのはまったくの考え違いです。
これは「学齢並みの英語力を身につけさせる事」や「落ちて行く日本語力にどう対応して行くか」等、様々な問題を生む「苛酷な選択」である事を認識した上で選択すべき事だと思います。
また、世界各国から様々な国籍の子供達が混ざった環境の中、果たしてその学校では「正しい英語」が話されているのか、また、文化的にはどの国の影響を受け、最終的に子供は「なに人になるのか」という事まで考えた上で、学校を選択するべきだと思います。
子供の精神的な打撃は大きい
確かに語学は脳が柔軟な子供時代に身に付けさせた方が上達が早いのは確かですが、「言葉のわからない環境」にほうり込まれた経験が子供に与える精神的な打撃は想像以上に凄まじいものです。実際うちの長男も「あんな思いはもう二度としたくない」と言っています。
言葉ができない事が原因で苛められたり、仲間はずれになったりする事は「多かれ少なかれ必ず起こる事」と覚悟しておかなければなりません。
親は正しく判断できない
我が家のケースのように「子供の学校教育の言語」が「両親のどちらの母国語でもない」場合、親には「子供の語学力を正しく判断する能力が欠落している」わけですから、特に注意を払う必要があると思います。
親の目からはペラペラに見えても、思わぬ落とし穴があるものです。
マルチ・ナショナルな家庭では
国際結婚の中でも特に「夫婦の共通語」が「夫婦どちらの母国語でもない」場合、夫婦の両方ともが「外国語」を使って意思疎通をしなければならないのは大変な事だと思います。
語学力にもよりますが、「言葉が足らない事」による誤解や行き違いなどが生じる可能性も当然高くなるでしょうから、互いに歩み寄る努力が普通以上に必要になると思います。
ただ、いかなる場合であったとしても、「子供が親に自分の複雑な心境を話す時の言語」だけは、必ず確保しておくべきだと思います。
ポイントは「混ぜない事」と「日本語を磨く事」
「言葉がチャンポンになる現象」は外国語習得の過程において必ず誰もが経験する事だと思います。
これは「言葉が稚拙な段階」の方が多く起こり、語学力が上がるにつれ、脳の中で引き出しが次第に分かれて来るので、各言語の切り替えがきちんとできるようになってきます。
「そういう状態に早くなる」ためには「言語を混ぜない事」です。私も一時はチャンポンになりましたが、今は英語を使っている時は英語だけで考えているので、頭の中で「翻訳」というプロセスは踏みません。
また、これは疎かにされがちですが、「落ちて行く自分の日本語を磨く事」も極めて重要です。「日本語(もしくは母国語)力を向上させる事が、外国語を上達させるコツである」と私は思います。
「長所」と「短所」の両方を知る
語学習得は大変だからこそ、「子供をバイリンガルに育ててあげたい」というのは誰もが思う親心。しかし、それは想像以上に苛酷な道であり、弊害の大きい道でもあります。
ただ、何事もそうですが、物事には必ず長所と短所があるものです。長所だけに目を向けて有頂天になったり、逆に短所だけに目を向けて悲観したりせず、両方の側面を正しく把握した上で、「自分や家族にとって最良の方法」を選択して行けば良いのではないでしょうか。
そして「最終的に目指すべき事」は「子供が幸せな人生を送る事」であった事を親が忘れてしまわないようにして欲しいと思います。
筆・滝つぼ