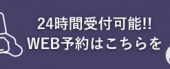子供に日本をどう
子供に「日本」をどう教えるか
海外での滞在も長期に及んだ場合、子供にとっては「多感な時期」の殆んどを海外で過ごす事になります。海外では親が努力しない限り、「日本」は自然には入って来ません。「子供に日本を教える事」は「片親だけが日本人の家庭」だけでなく、「両親とも日本人の家庭」にとっても、重要な課題となります。
日本のグループに参加する
我が家でもイギリスに住んでいた頃は、「子リス文庫」という「読み聞かせのグループ」に参加していました。子リス文庫では「日本の行事」に因んだ活動も入るので、子供達も子リス文庫の活動を通して日本を知る事は多く、今でも「ああ、それって子リス文庫でやったねえ」と、よく覚えています。

近所の日本人と仲良くする
イギリス時代は私もご近所の日本人家庭の方々と一緒にお茶をしながら子供達を遊ばせたものでした。
親や親類を当てにできない「海外」で子育てをするには、お互い「いざ」という時に助け合える「近所の親しい友人」を確保するのは大切な事です。
ただ海外での問題点は「日本人である事」以外に何も共通点がなく、「日本にいたら絶対にお友達にならないような人」でも「日本人だ」という事だけでお付き合いする事にもなる点です。後から関係が変にこじれないようにするには、なるべく「一定の距離を保ってお付き合いする事」だと思います。
イギリス時代は私もご近所の日本人家庭の方々と一緒にお茶をしながら子供達を遊ばせたものでした。
親や親類を当てにできない「海外」で子育てをするには、お互い「いざ」という時に助け合える「近所の親しい友人」を確保するのは大切な事です。
ただ海外での問題点は「日本人である事」以外に何も共通点がなく、「日本にいたら絶対にお友達にならないような人」でも「日本人だ」という事だけでお付き合いする事にもなる点です。後から関係が変にこじれないようにするには、なるべく「一定の距離を保ってお付き合いする事」だと思います。
アニメの威力を利用する
最近の「日本発のアニメ」の海外進出は目覚しいものがあります。DVD等は色々な言語を選択できるので、我が家では日本語で見ながら英語のサブタイトルを付けて日本語力の不足を補いながら楽しんでいます。
アニメは日本語だけでなく、日本の生活習慣や文化なども自然と入って来るので、我が家でも大いに利用しています。
最近の「日本発のアニメ」の海外進出は目覚しいものがあります。DVD等は色々な言語を選択できるので、我が家では日本語で見ながら英語のサブタイトルを付けて日本語力の不足を補いながら楽しんでいます。
アニメは日本語だけでなく、日本の生活習慣や文化なども自然と入って来るので、我が家でも大いに利用しています。
日本で体験入学をさせる (フラウHさんの体験談)
私の子供達が学校に通っていた頃は、夏休みに日本に里帰りをするのが楽しみでした。日本では7月の中旬迄学校があるので、子供達が2、3週間、体験入学をする事も可能でした。
子供達は日独のハーフで、毎週日本語補習校に通っており、一応日本語には不自由はしていませんでした。
日本での子供達の体験入学は、希望する学校に直接手紙などで連絡をとり、校長先生の許可が取れれば可能です。
地域にある帰国女子指定校などにあたってみるのも良いのですが、毎日通うので、近くの学校が便利でしょう。
我が家の場合は、子供達が毎年のように、学区内の小学校、中学校に通う事ができたので、子供同士でもお友達が出来、日本の友達も夏にドイツから子供達が来るのを楽しみに待っているようになりました。
学校も7月は短縮授業、プール、野外学習など楽しい行事も多いのですが、それだけ先生の負担も大きいので、体験入学中は私も出来るだけ学校に顔を出し、協力するように努めました。
その子供達も既に成人し、次男は今、京都大学大学院に留学していますが、「子供の頃の体験入学に感謝している」と言っています。 筆:フラウH
子供だけを日本に送り込む
我が家では長男が10才の時、長男だけを日本に送り込みました。「エスコート・サービス」のある航空会社を利用すれば、「子供の一人旅」は空港に迎えに来た両親に子供を引き渡すまで、ちゃんと面倒を見てもらえます。
1ヶ月もいたのは、ちょっと長すぎたようで、退屈したり、ホームシックになったりしてしまい、預かった両親も気を使って大変だったようです。
とは言え、長男はこの体験で随分と日本語が上達しました。私の両親との親しみも増し、日本の事も随分と理解したようで意義は大きかったと思います。
筆:滝つぼ
我が家の選択
我が家の選択
海外に住む日本人にとって「親のキャリア」と「子供の教育」を両立させる問題は常について回るものです。
日本国内で転校をするだけでも、新しい学校の学習進度や環境に溶け込むのは大変な事です。ましてやそれが、言葉や文化のまったく異なる外国への移転は、人間関係や環境、教育システムの変化だけでなく、状況によっては子供の「母国語」までをも変えさせなければならない場合もあり、海外生活は来る時も大変だが、帰る時もまた大変です。
こと教育の問題に至っては、子供の持って生まれた資質や能力、何歳で来て何歳で帰るか、親は両親とも日本人か、そうでないか等、それぞれの状況によって異なるので、「これが一番正しい方法」というものが存在しないものです。だからこそ、教育に対する親の正しい知識や認識、判断力が必要不可欠となります。
そんな時「よその家では何を決め手とし、どんな選択をしているのだろう。」という実際例をちょっと覗いて見るのも、時には大変参考になるものです。そこで今回は実際の「選択例」を幾つかご紹介致します。
田中家の選択
ドイツに駐在して5年になる田中さん
ご一家は、奥様と3人の娘を引連れて2000年8月に着任し、長女(17歳)がインターナショナルスクールを卒業する2006年6月に家族共々帰国する予定でした。
しかしながらこの春に本社のある部門のポジションをオファーされ、熟考の末に受入れることを決められたのだという事です。従って、田中さんは長女、三女(小6)奥様の3名と犬一匹を来年6月迄ドイツに残し、単身での帰任となります。
因みに次女(高1)は田中さんの元々の任期を考慮して、今春に家族より一足先に帰国させ、京都の高校大学一貫教育の高校へ寮住まいで通わせています。今回の田中さんの帰任により、田中家の5人と一匹は、広島、京都、デュッセルドルフと国内外で「一家離散状態」になります。
田中さんがこの意思決定をするに当っては、次の点を考慮されたそうです。
先ず娘たちの教育及び将来について。
因みに次女(高1)は田中さんの元々の任期を考慮して、今春に家族より一足先に帰国させ、京都の高校大学一貫教育の高校へ寮住まいで通わせています。今回の田中さんの帰任により、田中家の5人と一匹は、広島、京都、デュッセルドルフと国内外で「一家離散状態」になります。
田中さんがこの意思決定をするに当っては、次の点を考慮されたそうです。
先ず娘たちの教育及び将来について。
長女はインターナショナルスクールで習得した、日本の平均的高校生より若干優るであろう英語力と国際感覚を持って日本の大学へ帰国子女進学を予定。次女は今のペースで勉学と部活動に励み寮生活をエンジョイし、三女はドイツでの生活、日本人学校で学んだことと友達を大切にし、こちらで卒業式を迎えさせてやりたい。
他方、田中さんはこれまでの業務経験が充分生かせる広島本社の新たな部門で心機一転頑張りたいとのこと。因みに今回の選択は、グローバルに家族を支える奥様の存在なくしてはあり得なかったとのことです。
ということで、8月末から田中さんご一家の新しい生活がスタートします。家族がそれぞれ、別々の道を歩まれて、それぞれが成長し、更に家族の絆が強くなるであろう事を心から願っています。
ということで、8月末から田中さんご一家の新しい生活がスタートします。家族がそれぞれ、別々の道を歩まれて、それぞれが成長し、更に家族の絆が強くなるであろう事を心から願っています。
タイマンス家の選択
ご主人がベルギー人であるタイマンスさんご一家はご主人の仕事の関係で、しばらくはアメリカに住んでいました。でもアメリカの教育レベルは予想以上に低く、「アメリカ」という文化も歴史もなく、しかも危険な環境で暮らしていくストレスは何事にも変えられないという事で、ご主人は欧州勤務を希望して、英国に転勤となりました。
しかし英国はアメリカに比べて物価も高く、子供の私立の教育費や税金など、生活費全般がとても上がり、あまり満足のできる生活ではありませんでした。と同時に、タイマンスさんは仕事柄、各国を転々とする今の状況と、このままではベルギー人の父と日本人の母を持つ子供の母国語が、両親どちらの母国語でもない「英語」となってしまう事への危惧も強く感じていたという事です。
お子さんも6歳となった今、子供には一貫した教育システムとアイデンティティーを与えてやりたいと決意し、タイマンスさんはご主人の母国であるベルギーを「子供の教育の場」として選択する事にしました。
しかしご主人の仕事場が英国にある事は変えられません。仕方なく、今はご主人は英国に単身で残り、奥様とお子さんはベルギーで暮らして学校に通い、ご主人は週末にベルギーに帰って来るという生活スタイルを取る事にしたそうです。
お子さんはそれまで「英語」で教育を受けてきたので、母国語を変えさせるのは大変だし、言葉ができないことで苛められたり、つらい思いをする事もあったりしたとか。その涙を見た時、タイマンスさんは、「親の都合で、一度は変えさせた母国語だが、もう二度とこんな事はしない。
この子が流したこの涙を絶対に無駄にはさせない。」と心に誓ったのだそうです。そして「今後、子供にはベルギーの教育システムで一貫した教育を受けさせ、ベルギー人としての文化と誇りを身につけさせる」と、硬く決意したという事です。
それぞれの家庭で、それぞれの状況に応じ、それぞれの基準によって決めた、それぞれの選択。状況の変化に直面して、あれこれ悩むことはあっても、結局は「何が一番大切なのか」という「人生の急所」さえ押えていれば、自分が選択するべき道は自然に見えてくるものなのだと思います。
それぞれの家庭で、それぞれの状況に応じ、それぞれの基準によって決めた、それぞれの選択。状況の変化に直面して、あれこれ悩むことはあっても、結局は「何が一番大切なのか」という「人生の急所」さえ押えていれば、自分が選択するべき道は自然に見えてくるものなのだと思います。
2006年・筆:滝つぼ
日本での受験
日本での受験
サピックス進学教室・国際部・三鷹校室長:「小森慎一」筆
どの学校を志望するか
在外期間中にまず考えなければならないのが「どの学校を志望するのか」です。日本の学校情報は在外中には入手しにくいのが現状です。各高校のホームページなどで入試要項の確認はできますが、数値上のデータのみであり、生の「受験」の感触を得ることはできません。私どものような塾が実施する講演会や説明会などを利用して情報を収集するだけでなく、うまく先輩などのつてを利用して、その学校の生の雰囲気などを聴いておくと良いでしょう。
偏差値や知名度の高い学校が必ずしもお子様にとっての良い学校とは限りません。単に募集要項に掲載されているだけのデータではない情報をできる限り集めるようにしてください。一時帰国される場合には、実際に自分の目で学校を見学をされる事をお薦めします。
帰国子女枠の確認
志望校・受験校がある程度絞れたなら、その学校に「帰国子女枠」があるかどうかを確認します。「ある」場合には、帰国子女としての認定条件を確認してください。
例年、帰国子女枠受験の資格に「あと数日足りない(数日早く帰国してしまった)」という声を聞きます。一般入試と帰国枠入試では、難易度にかなり差があります。帰国時期はくれぐれも慎重に判断して下さい。
受験資格を得たら早目に帰国
志望校の帰国子女枠受験資格が得られたならば、できる限り早い時期のご帰国をお薦めします。特に関東圏の私立高校では、帰国子女枠も一般入試と同じ日程で、同じ問題を使用するケースが多く、数学や国語についてできるだけ国内生に近づける必要があるからです。
勉強は「高校に入学して終わり」ではありません。入学後はたいていの場合、帰国生も国内生も同一クラスになりますので、常に一歩先を見据えた学習が必要です。
「浅く広く」の学習法
次に、在外中の学習ですが、志望校の入試で必要な科目はもちろんなのですが、やはり理科や社会に関しても「浅く広く」という学習を心がけましょう。
例えば、慶應大学附属の3校(志木・義塾・女子)では、理科の知識があると読みやすくなる英文読解問題が出題されたりします。
また、開成高校や筑波大附属高校などは帰国子女枠でも「5科目の入試」となります。選択の幅を広げるためにも5科目のバランスをとった学習が望ましいと言えます。特に難しい問題集などは必要ありませんので、学校で支給される教科書をしっかり読む事が大事です。
帰国後の学習法
帰国後についてですが、志望校の過去問はしっかり研究しておいて下さい。
過去問は単に解けばよいと言うわけではありません。
大問が何問有るのか、リスニングはあるのか、どのような分野が主に出題されているのか、どの程度のレベルの知識を要求しているのか、といった事を分析し、その分野や似た形式の問題を集中的に練習しておく事にこそ、過去問を解く意義があります。実際に時間を計って解くのは、12月~1月の直前期で構いません。
「確実に合格できる学校」も
もう一つ大切なのは、「確実に合格できる学校」を受験する事です。帰国子女枠が如何に合格しやすいと言っても不合格になっている方もいるわけです。
条件としては、「3年間そこに通う事になっても、本命校に通っていたら3年後に進学していたであろう大学に合格しうる力をつけてくれる高校」かつ「本命よりも受験日が先」そして「何があっても(学力的に)絶対に合格できる高校」を選ぶ事です。
以上、私の経験に基づき述べましたが、多少でも参考にして頂ければ幸いです。
筆:小森慎一
シトワエンドュ
シトワ エン ドュ モーンド(世界の住人)
私は日本人でありながらイギリス人と結婚し、今はフランスで生活している。そんな親を持つ子供達にとって、こんな事はとても迷惑な話だ。本当の意味でうちの子供達はイギリス人でもなく、日本人でもなく、フランス人でもない。だから自分のアイデンティティーを持てなくて可愛そうだという見方もできる。
そのため我が家では子供達に、「じゃあ、お前は一体、なに人なんだ?」と聞かれたら、「シトワ エン ドウ モーンド」つまり、「世界の住人だ」と答えなさい、と教えている。先ほどと逆の見方をすれば、うちの子供達はイギリス人でもあり、日本人でもあり、文化的にはフランス人でもあるという、欲張りで恵まれた環境にあるという見方もできるわけだ。
過去の歴史を振り返って見れば、これまでに引き起こされた戦争はすべてこのアイデンティティー、つまりグループ意識が原因となっている。そしてそれはある時は宗教として、ある時は国民として、またある時は肌の色など、種類は様々であるが、すべてはこの「アイデンティティー」に起因している。自分と同じグループの人々さえ幸福ならば、あとの人はどうなってもいい。死のうが苦しもうが、ざまあミロ、というわけだ。
本来、宗教というものは、人間が幸福になるためにあるべき物なのに、これまでの戦いの殆どがこの宗教上の問題から発足しており、それは現在でも続いている。自分の信者だけを救い、信者以外はどうなってもいいなんて、ふざけた話だ。神格の高い本当の神様であれば、信者であろうがなかろうが、世界人類、ネコも杓子も、すべてを救って下さるはずだ。信者以外を排斥しようというのなら、それは神様の意図ではなく、時の指導者の意図によるものであり、信者は利用されているだけに過ぎない。
外敵をつくる事で内部を団結され、その仲間意識を利用して、時の支配者は自分の勢力をつけて来た。ヒットラーはユダヤを、日本人は中国人や韓国人を、白人は黒人を、それぞれ虐待した。これらも全ては自分達以外の人種は人間ではないという考え方、つまりは「アイデンティティー」に起因している。
ところがうちの子供達のように世界各国に血のつながった親戚や、友人がいたらどうだろう。イギリスに祖父母や叔父、叔母、イトコ達がいるのと同様に日本にもいる。オーストラリアにもイトコがいるし、アメリカにも遠縁があり、フランスにもイギリスにもベルギーにも大勢のお友達がいる。
私とて、その他にはポーランド人、ドイツ人の友人もいるし、その他にも色々な国の知り合いがいる。自分にとって「この人が傷ついたら直接悲しい」という人達が世界各国に散らばっていたら、どこの国とも戦争なんてする事はできない。
人類愛とか世界平和といった哲学的な言葉を使うと実感のわかない概念だったとしても、うちの子供達に「もし、イギリスと日本が戦争になったら、日本のじいちゃんやばあちゃんが死んでも、イギリスのグラニーとグランダディーが死んでもどっちも悲しいでしょ?」と聞けば、迷わず「うん」と答えが返って来る。
人類愛とか世界平和といった哲学的な言葉を使うと実感のわかない概念だったとしても、うちの子供達に「もし、イギリスと日本が戦争になったら、日本のじいちゃんやばあちゃんが死んでも、イギリスのグラニーとグランダディーが死んでもどっちも悲しいでしょ?」と聞けば、迷わず「うん」と答えが返って来る。
そして、「人間には誰にでも家族がいて、それと同じ気持ちを皆が持っている」と説明すれば、世界中の人達の幸福を願うべきなのだという事を単純に理解する事ができる。
とかく狭くて閉鎖的な環境の中だけに暮らしていれば、気心の知れた「うちわ同士」には安心感を持ち、「よそ者」に対しては排他的になるものだ。そしてその「よそ者」にも家族がいて、親戚がいて、愛する人達がいるのだという、余りにも当たり前の事実を忘れてしまう。
但し、ここで忘れてはならないのが、このアイデンティティーには、「他のグループに対して自分のグループの方が優越である」という思い込みが誰にでも根底にあるという点だ。
西洋諸国では「自分達は世界のリーダーであり、世界中の平和は自分達の肩にすべてかかっているのだ」という傲慢な自尊心の元に無関係な他国の問題に武力介入しては余計に状況を悪化させて来たし、また「自分達の優れた文化を可愛そうで劣っているほかの文化の人に教えてあげて、幸せにしてあげなければならないのだ」という使命感までをも伴うおせっかいのために、多くの国の人々が価値観を喪失させられ、迷惑を被ってきた。
日本は戦争に負けた事によって、突如として西洋式の生活習慣や考え方を押し付けられた。それによって戦後、日本人はアイデンティティーを失い、価値観の拠り所を求めてずっと苦悩して来た。
とかく狭くて閉鎖的な環境の中だけに暮らしていれば、気心の知れた「うちわ同士」には安心感を持ち、「よそ者」に対しては排他的になるものだ。そしてその「よそ者」にも家族がいて、親戚がいて、愛する人達がいるのだという、余りにも当たり前の事実を忘れてしまう。
但し、ここで忘れてはならないのが、このアイデンティティーには、「他のグループに対して自分のグループの方が優越である」という思い込みが誰にでも根底にあるという点だ。
西洋諸国では「自分達は世界のリーダーであり、世界中の平和は自分達の肩にすべてかかっているのだ」という傲慢な自尊心の元に無関係な他国の問題に武力介入しては余計に状況を悪化させて来たし、また「自分達の優れた文化を可愛そうで劣っているほかの文化の人に教えてあげて、幸せにしてあげなければならないのだ」という使命感までをも伴うおせっかいのために、多くの国の人々が価値観を喪失させられ、迷惑を被ってきた。
日本は戦争に負けた事によって、突如として西洋式の生活習慣や考え方を押し付けられた。それによって戦後、日本人はアイデンティティーを失い、価値観の拠り所を求めてずっと苦悩して来た。
民主主義とか自由とか個性の尊重とか、これらの思想は元々が自分達の社会から必然的に生み出された概念ではないから、表に掲げているだけで、実際には誰にもよく理解できていなかったため、「自由イコール自分勝手」という単純な方式をもってして、多くの人々が利己的になり、物欲主義に陥ってしまったのだ。
しかし、これらはたまたま西洋人が時の権力を握ったからそうなっただけで、日本人が権力を握れば日本式に、ユダヤ人が握ればユダヤ式に、アラブ人が握ればアラブ人式に、それぞれが同じ事をしたはずだ。
だが本当の意味で「アイデンティティーを持つ」という事は、他人のアイデンティティーの存在をも認め、それを尊重しなければいけない。うちの子供達は日本の家では玄関で靴を脱ぎ、お風呂は外で洗うが、イギリスでは靴のままで、お風呂の水は外に出してはいけないという事を身体で知っている。
靴を脱ぐ方がいいのか悪いのか、お風呂は外で洗う方が良いのか悪いのか、優劣をつけようとすれば争いとなる。こうした違いに優劣をつけるのではなく、違いは違いとして理解する事が他人のアイデンティティーを尊重する第一歩だ。
「世界の住人」である私達はそれを「人権の尊重」とか「相互文化の理解」などといった哲学的概念としてではなく、もっと低次元で身近な、当たり前の常識として知っている。つまりは、人と人、文化と文化をつなぐ架け橋となる事のできる素晴らしい人種なのだ。だから「あなた達は世界の住人である事に誇りを持って生きていきなさい」と、私は子供達にそう教えている。
しかし、これらはたまたま西洋人が時の権力を握ったからそうなっただけで、日本人が権力を握れば日本式に、ユダヤ人が握ればユダヤ式に、アラブ人が握ればアラブ人式に、それぞれが同じ事をしたはずだ。
だが本当の意味で「アイデンティティーを持つ」という事は、他人のアイデンティティーの存在をも認め、それを尊重しなければいけない。うちの子供達は日本の家では玄関で靴を脱ぎ、お風呂は外で洗うが、イギリスでは靴のままで、お風呂の水は外に出してはいけないという事を身体で知っている。
靴を脱ぐ方がいいのか悪いのか、お風呂は外で洗う方が良いのか悪いのか、優劣をつけようとすれば争いとなる。こうした違いに優劣をつけるのではなく、違いは違いとして理解する事が他人のアイデンティティーを尊重する第一歩だ。
「世界の住人」である私達はそれを「人権の尊重」とか「相互文化の理解」などといった哲学的概念としてではなく、もっと低次元で身近な、当たり前の常識として知っている。つまりは、人と人、文化と文化をつなぐ架け橋となる事のできる素晴らしい人種なのだ。だから「あなた達は世界の住人である事に誇りを持って生きていきなさい」と、私は子供達にそう教えている。