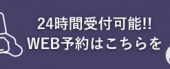バイリンガルの科学
バイリンガルの科学
小野博著(工学医学博士)
講談社発行 ブルーバックスB-1011
科学的実証例に基づいて
小野博著(工学医学博士)
講談社発行 ブルーバックスB-1011
科学的実証例に基づいて
バイリンガルの実態を分析した本。
●語学と知能の相関的闊達
海外に住む日本人にとって言語教育の問題は必ずついてまわるものです。しかし子供に多数の言語を習得させる事を子供の性格形成や知能の発達にまで関連づけて考える人は少ないようです。
大学時代、教育心理の授業で教授が突然言い出した言葉に私は愕然としました。それは「バイリンガルの子供は知力の発達が遅れる。何故ならば人間は言葉を使って物事を考えるからで、習得言語を2つに広げると、両方の言語の発達程度が低くなるので、難しい問題を考えようとする時にどちらの言語の発達も未熟となって頭が混乱してしまう。」というものでした。
当時、一生懸命に英語を勉強していた私は「母国語を持たないセミリンガルの弊害」という事をその時、初めて知ってショックを受けてしまいました。
海外に住む日本人にとって言語教育の問題は必ずついてまわるものです。しかし子供に多数の言語を習得させる事を子供の性格形成や知能の発達にまで関連づけて考える人は少ないようです。
大学時代、教育心理の授業で教授が突然言い出した言葉に私は愕然としました。それは「バイリンガルの子供は知力の発達が遅れる。何故ならば人間は言葉を使って物事を考えるからで、習得言語を2つに広げると、両方の言語の発達程度が低くなるので、難しい問題を考えようとする時にどちらの言語の発達も未熟となって頭が混乱してしまう。」というものでした。
当時、一生懸命に英語を勉強していた私は「母国語を持たないセミリンガルの弊害」という事をその時、初めて知ってショックを受けてしまいました。
●成功するバイリンガル教育
でも、やはり自分が母親になってみれば、子供をバイリンガルにさせたいという欲も出るし、見栄も働くものです。では、どうすれば、子供に上手に言語を身に付かせ、尚且つ子供が幸せになれるでしょうか。これは誰にとっても是非知りたい事です。この本はそんな疑問に、科学的に実証したデータを使って答えてくれます。
たまたま外地に長く住んでいたからと、自分の狭い経験だけで本を書いたりする人もいますが、個人の知り合える範囲など、たかが知れているし、子供によってまったく違うので、あまりあてにもならないものです。筆者が世間で信じられているバイリンガルに対する常識を敢えて「神話」と呼ぶのも、世間一般のそういった盲目的な信じ込みを比喩しての事です。
でも、やはり自分が母親になってみれば、子供をバイリンガルにさせたいという欲も出るし、見栄も働くものです。では、どうすれば、子供に上手に言語を身に付かせ、尚且つ子供が幸せになれるでしょうか。これは誰にとっても是非知りたい事です。この本はそんな疑問に、科学的に実証したデータを使って答えてくれます。
たまたま外地に長く住んでいたからと、自分の狭い経験だけで本を書いたりする人もいますが、個人の知り合える範囲など、たかが知れているし、子供によってまったく違うので、あまりあてにもならないものです。筆者が世間で信じられているバイリンガルに対する常識を敢えて「神話」と呼ぶのも、世間一般のそういった盲目的な信じ込みを比喩しての事です。
●バイリンガルの神話
筆者の説く「バイリンガルの神話」とは:
・帰国子女は皆、英語ができ、発音もすばらしい。
・国際結婚の子供は皆、バイリンガルになれる。
・二つの言語がペラペラ喋れる人は、2言語を使って何でもできる
・日本国内だけの外国語学習でバイリンガルになるのは難しい。
・幼児のうちに外国語を学習させないと発音は良くならない。
筆者の説く「バイリンガルの神話」とは:
・帰国子女は皆、英語ができ、発音もすばらしい。
・国際結婚の子供は皆、バイリンガルになれる。
・二つの言語がペラペラ喋れる人は、2言語を使って何でもできる
・日本国内だけの外国語学習でバイリンガルになるのは難しい。
・幼児のうちに外国語を学習させないと発音は良くならない。
●科学的実証例に基づく理論
筆者は自分の工学、理学で得た理系の研究手法をモトに、日本人の日本語と外国語とのバイリンガルに関してより深く探るため、言語学、音響学、外国語教育学、日本語教育学、障害児教育学など、発達と言語にまつわる多くの分野の科学的な根拠を組み合わせて分析し、調査研究で得られた結果が説明できる新しい理論を構築しようとしました。
そのために、人間の言語の習得と教育の始まりとの関係、日本語と外国語間の距離、子供の母国語の習得と感受期の関係、日本人の学校教育にいける外国語学習などについて、従来の外国語学習の研究の視点では欠けていた点にも注目して、海外駐在、帰国子女の調査結果を分析、考察して本書をまとめました。
筆者は自分の工学、理学で得た理系の研究手法をモトに、日本人の日本語と外国語とのバイリンガルに関してより深く探るため、言語学、音響学、外国語教育学、日本語教育学、障害児教育学など、発達と言語にまつわる多くの分野の科学的な根拠を組み合わせて分析し、調査研究で得られた結果が説明できる新しい理論を構築しようとしました。
そのために、人間の言語の習得と教育の始まりとの関係、日本語と外国語間の距離、子供の母国語の習得と感受期の関係、日本人の学校教育にいける外国語学習などについて、従来の外国語学習の研究の視点では欠けていた点にも注目して、海外駐在、帰国子女の調査結果を分析、考察して本書をまとめました。
●科学的実証による結論
その結果、著者が結論として得たものは、
(1)子供の知的な発達が自然に行われるためには、少なくとも小学生の時代は1つの言語で教育を受ける事が望ましい。
(2)将来仕事で使えるバイリンガルになるには、中高校まで日本語で教育を受けた後、海外で必要に応じて外国語学習を実践した人の方が到達しやすい。
というものです。
その結果、著者が結論として得たものは、
(1)子供の知的な発達が自然に行われるためには、少なくとも小学生の時代は1つの言語で教育を受ける事が望ましい。
(2)将来仕事で使えるバイリンガルになるには、中高校まで日本語で教育を受けた後、海外で必要に応じて外国語学習を実践した人の方が到達しやすい。
というものです。
●バイリンガルの育て方
「とにかくバイリンガルにする事がこの子のため」と、必死にがんばってきた方にとっては、自分が信じていた事を根底からくつがえされたような思いがするかも知れません。でも筆者は「現地の学校には行かせるな、小さい子供に英語を教えるな」と言おうとしているのではなく、「日本人のバイリンガルの問題点」というものを整理して説明し、セミリンガルにならないための対策をも紹介してくれています。
同じ努力をするなら、こういった知識を踏まえた上で、語学を教育していきたいものです。私達は過去に同じように努力した人達が失敗した実例に学び、既に立証されている事と同じ失敗をわざわざ自分の子供にさせないようにしたいものです。
教育に熱心になるあまり、子供から出ているサインを見過ごしてしまうケースは多いものです。この本は海外で子育てをする日本人の必読の書と言えると思います。
「とにかくバイリンガルにする事がこの子のため」と、必死にがんばってきた方にとっては、自分が信じていた事を根底からくつがえされたような思いがするかも知れません。でも筆者は「現地の学校には行かせるな、小さい子供に英語を教えるな」と言おうとしているのではなく、「日本人のバイリンガルの問題点」というものを整理して説明し、セミリンガルにならないための対策をも紹介してくれています。
同じ努力をするなら、こういった知識を踏まえた上で、語学を教育していきたいものです。私達は過去に同じように努力した人達が失敗した実例に学び、既に立証されている事と同じ失敗をわざわざ自分の子供にさせないようにしたいものです。
教育に熱心になるあまり、子供から出ているサインを見過ごしてしまうケースは多いものです。この本は海外で子育てをする日本人の必読の書と言えると思います。
ゲーム脳の恐怖
ゲーム脳の恐怖
森昭雄(日本大学文理学部教授)著 NHK出版 生活人新書
森昭雄(日本大学文理学部教授)著 NHK出版 生活人新書
現代社会に生きる我々にとって、テレビやビデオ、ゲームやパソコン、携帯電話などは既に生活の一部となってしまっています。しかしその背景にはゲーム等のやりすぎで脳が犯されておかしくなっていく子供達がいます。
ここでは、2003年1月27日読売新聞、eライフで森先生自身が書き下ろしているエッセイの抜粋により「ゲーム脳」の恐ろしさを簡単にご紹介致します。
「ヒトの脳には、「前頭前野」と呼ばれる場所がある。ちょうど額の内側付近にあたる。創造性や理性、特に作業記憶に直接関係している領域とされ、人間らしさを維持するのに大切な所だ。
ところが、毎日、長時間テレビゲームをしている人の額に脳波用の電極をあて、脳波を測定してみると、神経細胞の興奮性を反映しているβ波が前頭前野から殆ど出ていない。さらにゲームを始めるとまったく出なくなった。こうした状態を私は「ゲーム脳」と名づけたのである。
ゲームのやり過ぎは前頭前野の活動を低下させてしまうらしい。お酒も飲みすぎは病のもとになるのと似ている。
テレビゲームの中には、一時的にβ波の活動を上昇させるものもあるようだ。
だが慣れて来ると脳は適応してゲームに対して効率よく神経回路が形成されてしまう。ゲーム脳の人のβ波は、私がこれまで調べて来た痴呆症のお年寄りも更に低い。そしてゲーム暦の長い人ほど、ゲーム脳になる傾向が強い。幼児期にゲームを始めると、ゲーム脳になるのに月日はかからないだろう。
ゲーム脳と判定された大学生のA君。
小学校1年から大学3年まで15年間、毎日2時間以上はゲームをやっていた。A君は普段ボーっとしていることが多く、表情が乏しく、口数も少ない。忘れ物をすることも多く、定期券、財布、鍵などもよく忘れるという。
また、ゲーム脳の子供は感情のコントロールがきかず、キレやすい。脳は高次な機能を司る「大脳皮質」と、「旧皮質」、「古皮質」に分けられる。古い皮質は下等動物でも持っており、本能的な行動に関係している。これに抑制をかけているのが、実は大脳皮質に含まれる前頭前野なのだ。」
これが恐ろしい「ゲーム脳」の実態です。この現象はゲームだけでなく、テレビ、ビデオ、携帯メール、パソコンでも、脳に同様の影響を及ぼすというのだから恐ろしいものです。
私も情報誌の締め切りの時は毎日何時間もパソコンに向かって入力するのですが、先月はある朝突然頭がフラフラになって立ち上がれなくなり、意識が朦朧とし、吐き気までしました。
脳は使えば使う程発達するのだそうで、逆に「便利な世界になると人間の脳も小さくなっていく」と森教授は危惧されているそうです。そう言えば、優れた方向感覚を持つ私の夫でさえ、日本で3週間カーナビに頼って運転してフランスに帰国したら、まったく方向感覚を失ってしまいました。
逆に脳に良い刺激を与えるとされる事は、森教授の研究によれば、「お手玉」、「外遊び」、「スポーツ」、「読書」、「音楽鑑賞」、「自然とのふれあい」、「ホタルを見る」などだという事です。中でも「本を読む事」は前頭前野を活性化させるため、脳に大変良い刺激を与えるのだそうで、「ボケ防止のためにどんどん本を読む事をお勧めする」ということです。
現代に生きる私達はこうしたIT機器と、今後どうやって上手に付き合っていけばいいのか、、、。これからの時代に入って考えていくべき重要なテーマであるようです。
カプラ講習会
カプラ講習会レポート
危ないからと遊ばせない大人達、その中で育ってしまった遊べない子供達。今、大事な何かが失われ壊れつつあるのでは、、。
この事をテーマに日本から吉川静雄講師を招き、2005年6月にミュンヘンとデュッセルドルフの2箇所で行われたカプラの講習会。
当日、ちびっ子達はインストラクターのお姉さんと一緒にカプラを楽しみ、大人達は吉川さんから人生にとって大切な事を沢山教えて頂きました。
吉川さんはトップセールスマンとして活躍していましたが、健康を害した事から「食」に関心を持つようになり、「自分が納得のいく本物だけを販売したい」という意欲に目覚めたという事です。
そして今は、「子供の体力向上と知情意豊かな人間形成」を目指して、子供の脳の発達に最良な玩具「カプラ」と「安田式遊具」の普及に努め、食生活や環境問題等を含めた全人的なテーマの基に各地で精力的に講演会を行っています。
講習会を通して私に最も強く伝わって来たメッセージは、「何代も何代も繋がる先祖がいたから、今の自分が存在するのだ」という事。
人間はまず母親のお腹の中で、三十六億年の系統発生を繰り返して、最後に人間となって生まれてくる。
最初は卵、それが次々と細胞分裂をして、魚のような形となり、トカゲのような形から手足が発達して、猫や犬のようになり、猿のようになって最後に人間となります。
生まれたての赤ちゃんは何もできないが、やがてハイハイが始まって4つ足となり、2足歩行ができるようになる、、、。
つまり人間の成長の過程は、人類の進化の過程でもあるわけです。
横体四足歩行から直立二足歩行へと進化する事により、頭は真上に位置するため数倍の重さまで発達が可能となり、しかも前肢は腕、手、指となって自由自在複雑精緻な動作が可能となりました。
猿から進化して来た私達人間は、かつては木の上に住んでいました。だから「樹上遊び」を始めとした「外遊び」を体験する事は子供が人間として成長する過程において大変重要な行為なのだそうです。
脳の生育は3歳までに約7割、10歳までには殆ど完成してしまいます。発育刺激としては「楽しい身体活動による実体験」が最も効果的なのだそうで、つまり「幼い時から毎日が楽しい活動的なものである事」が脳の正常な発達には欠かせないと言えるのだそうです。
昔は日本でも近所で色々な年齢の子供達が一緒に外で遊び、年齢が上の子供が小さい子の面倒を見たりする事によって社会性やルール、人間関係や思いやりなど、人間として基本的で大切な多くの事を学んだものでした。
しかし、現代では、こうした「当たり前の環境」は現代社会では、努力をしなければ子供に与えてやれない「希少な環境」となっています。
そんな現代の環境の中、子供にとって本当によい玩具として吉川さんが確信できたのが「カプラ」なのだそうです。
また、同様に「安田式遊具」とは、もと小学校の校長先生であり、「外遊び体育遊具協会」を設立した安田祐治先生が研究開発した遊具で、子供がこうした進化の過程を十分に体験できるように設計されており、こちらも子供の発達には最良の玩具だとか。
地上より高い所での運動であるから、恐怖心の克服、技の多様さ、複雑巧妙な変化など、興味深く、満足感絶大の遊びとなるように工夫されています。
危険を避けるのが安全ではありません。危険を認知し、適切に対応する判断と処置能力を身につける事が真の意味での安全なのです。
こうして生命の進化の過程を辿って行けば、そこにはすべての答えがあるものです。肉食動物の爪はとがっているが、草食動物の爪は平たくなっています。
つまり身体を見れば何を食べるべき動物なのかが、ちゃんとわかるのです。
人間の歯並びを見れば、人間がどんなものをどのくらいづつ食べれば良いのかの答えがそこにはあるものです。8本の前歯は野菜をかじる為、4本の犬歯は肉を噛み切るため、20本の臼歯は穀類を噛み砕くためにあるのだから、この歯の割合と同じように、穀類5、野菜類2、肉類1の割合で食べれば良い、という事です。
最近、騒がれている「牛乳」にしても、本来牛乳は牛の子供に飲ますためのものである事を考えれば、牛乳は人間が飲むべきものでない事は自ずと納得が行くというものです。
本来「ごはんと味噌汁」を食べていた日本人が「パンと牛乳」を食べ始まった背景には、戦後のアメリカが「国内の余剰小麦問題を解決したい」という思惑があったのだそうです。
そのため私達の給食にはパンと牛乳が導入され、「何でも洋風が素敵」というあの当時の風潮は、占領軍による「日本国民骨抜き政策」の一環だったのでした。
しかし日本人の身体は西洋人とは違います。日本人にとって先祖代々そうして来たように米を食べる事はとても大切な事なのだという事です。
「国際人、国際人」と騒がれる昨今ですが、真の意味で国際人になるためには、まずはちゃんとした日本人になる事が大切だと思います。
自分の国の文化や社会を理解し、国民としての誇りを持ってこそ初めて、他文化を持つの人間の事も理解でき、他文化を尊重する事もできるようになるものだと私は思います。
この講演会を通して私は多くの事を学んだが、吉川さんは私が自発的に探究心を持つ方向へとご指導して下さいました。「吉川さんのメッセージを一人でも多くの方に伝えたい。」そんな気持ちで一杯になった私でした。
吉川さんの推薦図書
*「学校で学びたい歴史」 斉藤武夫著・産経新聞
*「新歴史の真実」アインシュタインの見た日本・前田徹著
*「大江戸えころじー事情」 石川英輔著・講談社
人間にとって出会いはとても大切である。時には人生を根底から変える程の出会いをする事もある。良い本との出会いも、人間にとっては大切な出会いの一つである。よき出会いを。
子供の自尊心
1. 子供の自尊心を育てるには
~イギリスの子育てサポートグループ
「ペアレンツリンク」の研究レポート~
親家業ほど重要ではあるけれども疲れるものはありません。天使のようなお子様に恵まれた方ならいざ知らず、我が家の様にギーギーガーガー動物園状態になっている場合は、どうやって怒鳴らずに日々子供と付き合って行ったらよいのかが重要な課題となります。
子供との関係がうまく行かない、子供がどうも自信がない等といった悩みは、親にとってはとてもつらいものです。その上、親が元気でないと子供にも反映します。
そこで、私が参加した「ペアレンツリンク」という英国人の母親セミナーの内容を日本語で簡略にご紹介致します。
自分を鏡に写すとき、鏡の中の自分を他人の目から見る実態より、その時の自分の心の状態によって、自分にとっての事実が異なるものです。
私なりに定義すれば自尊心とは「いかに自分が自分に満足するか」という事だと思います。
生まれたての赤ちゃんは自分を知りません。自分に送られるメッセージから自分がどんなものなのかを判断しようとします。
ですから愛情を注げば「自分は愛情を注ぐに値するもの、大切なもの」と信じ、それが精神の安定と発達に重要な役割を果たします。逆に、常に否定され批判され続けた経験は「自分は駄目で価値のないもの」と信じさせ、自信を失わせます。
役に立つからとか、いい子だからとかいった条件付きではなく、ただ自分の存在自体が価値のあるものだと信じる事が自尊心の第一歩なのです。英語ではGolden Centreと呼ぶ自分の奥底に存在する実態の価値を認めることです。
親がどんなに願っても、子供が苦痛を味わう経験を阻止し切れるものではありません。魚を与え続ける事と、魚を取る道具や手段を与え、自分で魚が取れるようにしてやる事と、どちらが真の意味での手助けとなるのでしょうか。
ご自分が自信を失っている時、どんな事が助けとなり、逆にどんな事が不快だったかを時には見直す事も大切です。子供が感情的になっている時には理屈で諭そうとするよりは、まずは勘定の問題に焦点を置くと良いでしょう。
嫉妬や怒り等のマイナス感情も、感情を持つ事自体を否定してしまうのは良くありません。子供はその感情を持つ自分がおかしいと思い、自分の感情や自分自身の価値を否定する事になります。
まずは子供がその感情を持っている事に対して理解を示してやりましょう。その上で、そういった感情に対処する方法を教えてやると効果的です。
子供は自分を認めてもらったことで満足し、合理的な解決策を納得できるものです。こうした経験の積み重ねにより、子供は思い通りにならない事に対する自分なりの感情処理方法を身につけて行きます。
頭の中にピンクの象を描いて下さい。そして次にそれを打ち消してください。まだ象は頭の中に残っていますか? 人間は言葉で行動のイメージを作るものです。
そのため、子供に注意する時には「走るな、こぼすな」等の否定文を使うより、「歩きなさい、両手で持ちなさい」と言った肯定文を使う方が言葉による自己暗示を効果的に利用できます。
すべての行為は時と場合によってすべきであったり、してはいけなかったりするもので、「投げる、走るなどの行為も、それ自体が「禁止の行為」なわけではありません。
行為自体を罪悪視するのではなく、「投げるのはボールね。走るのは運動場でね」といった肯定的な行動と併せて子供に想像しやすいイメージを与えてあげましょう。
「あなたのせいでお母さんは頭が痛い」など、子供を攻める叱り方は子供に「責任を他人に押し付ける方法」を教えているようなものなので、注意しましょう。
逆に、「お手伝いしてくれたから、お母さんは嬉しいわ」というような言い方は、一見、褒めているように見えますが、実際には「条件付の愛」という印象と、「常にその行為を繰り返す事を期待されている」というプレッシャーを子供に与える可能性もあるので、要注意です。
褒める時は「上手ね、偉いね」と言うだけでなく、どんな事をしたどんな点がどのように良かったのかといった具体的な褒め方を心がけると、子供の自尊心を育てるのに大変効果的ですので、ちょっと試してみて下さい。
子供にレッテル
2 子供にレッテルを貼る
~イギリスの子育てサポートグループ
「ペアレンツリンク」の研究レポート~
~イギリスの子育てサポートグループ
「ペアレンツリンク」の研究レポート~
日常の生活を振り返ってみると、頭の悪い子だの駄目な子だのと、私達は何の抵抗もなく子供の人格に対して単純に分類わけして、子供にレッテルを貼っているものです。
では、ここでご自分が子供だった頃のことを思い出してみましょう。悪いレッテルを貼られた時、どのように感じられたでしょうか。
「劣等感を持ったり、自分を過小評価するようになった」、「そう言われて頭に来たから、わざとそうしてやれと余計に悪くなった」、など、マイナスの結果が殆どでした。中には「奮発してそうじゃないと証明しようと努力した」という前向きな意見はあったものの、これもいくら努力しても否定され続けてしまうと、結局は自信を失う結果となってしまうようです。
では、逆に良いレッテルを貼られた時はどうでしょうか。「自信をもった」、「自分を過大評価して鼻が高くなりすぎた」等という意見の他に、「そう言われてそうせざるを得ないプレッシャーに苦しんだ」という人もいました。
ある人は『親切な子』と言われて来たので、弟や妹が自分達の分のお菓子を食べ終えてなお、彼女に「ちょうだい」とねだって来ても、「これは私の分よ」と断る事が、つい最近になるまでできなかったのだそうです。
つまり、周囲から「この子は常にこうする」と期待されてしまうと、そうしなかった、またはそうできなかった時に自分の存在価値を失ってしまう事を意味するわけで、子供にとってそれは大変なプレッシャーなのです。
この場合、得に危険な事は「自分自身に嘘をついている事に本人すら気がつかないこともある」という点で、親が本人の意思を確認したりしても、子供は「親が子供にそう答えてもらいたい」と思っている答えを本能的に読み取ってその通りに答えたりするので、隠された子供の本心を本人から聞き出す事ができない場合もあるという点です。
子供にとって親から褒められる事や親の感心を引く事は死活問題であり、その為にはそれにそぐわない自分の性格や感情は存在すべきものではなく、心のバケツに突っ込んで蓋をしてしまい、なかった事にしてしまうものなのです。
しかし、それを長年くり返していくうちに、バケツの中に閉じ込められた本当の自分は行き場もなく蓄積されていく一方ですから、そのうちに中で腐食し、ガスまでたまり、いずれ大爆発を起こしたりする事もあるわけです。こうして「ある日突然、人が変わってしまって周囲がびっくりする」という事が起こったりするものだと思います。
人間には誰にも様々な側面があるものであり、環境や立場、相手によっても、また、その日の気分によってすら正確も態度も能力までも変化するものです。にもかかわらず、「お前はこういう奴だ」と一方的に決め付けることは、子供の微妙な変化を受け止めてやる努力を怠っている事でもあります。
つまりは一つの事象ですべての人格を評価するのではなく、その場その場でやった事や出て来た結果に対してのみ、叱ったり褒めたりするように心掛ける事が、子供にへんなコンプレックスを与えたり、性格をゆがめたりせず、子供の素直な成長を促す為にとても大切な事なのです。
叱る時は単に「悪い子だ」と言うのではなく、「今、あなたのした事は悪い事であり、直して欲しいから注意しているのであって、貴方を嫌いになったわけではない」という点を明確にして叱る事が大切です。
一方、褒める時は、その結果や行為を繰り返す事を期待しない、そうでなかったからと言って親からの愛情が変わるわけではないという逃げ場を子供に与えてやるなどの配慮をしながら褒めると良いでしょう。
レポーターより:
親の側からすれば、誰もが子供に良かれと思ってやっている事なのに、ほんの少しの言葉の使い方の違いで、こんなにも違った結果を招くものだとは、、、子育ては奥が深く、また、これは子育てだけではなく、職場のボスと部下の人間関係にも通じるものがあり、大変関心させられました。
理想的母親像
3.理想的母親像という名の罠
~イギリスの子育てサポートグループ
「ペアレンツリンク」の研究レポート~
~イギリスの子育てサポートグループ
「ペアレンツリンク」の研究レポート~
初めて子供が生まれた時には喜びと感動に満ち溢れ、「この子がただ健康で幸福ならそれで充分だ」と思ったのも束の間、他の子供の成長と比べて焦ったり悩んだりと、いつの間にか競争社会の中にはまってしまうという事はよくある事です。
世に言われる「理想的な母親」というのは、具体的にどんな要素が上がるでしょうか?
「常に子供がお行儀がよく親の言う事をきく」、「常に規則正しい生活をさせる」、「早く読み書き勘定ができるようにさせる」、「常に子供と一緒にいる」、「早くおむつをはずさせる」、「離乳食はすべて手作り」、「母乳だけで育てる」など色々と挙げられますが、これらのすべてを実際に実行なさっている方がいらしたら、その方はそれこそ偉大です。
私はと言えば、全部が失敗。私なりにがんばったのですが、やっぱり無理でした。「理想」実行できない事を「失敗」と呼びますが、この「敗北感」が「理想的な母親像」という名の罠に陥る最大の原因となるのだそうです。
もう一度、理想像の要素を振り返ってみましょう。「常に」とか「絶対に」ではなく、「できるだけ」とか「なるべく」という言葉を添え直してみると、自分でも何とか達成できていた事も増えるのではないでしょうか?
この「達成感」が大切なのだそうで、「この位できれば、まあいいか」とか「できなかったけど、人生、このくらいの事は重大な過失ではないから、まあいいか」といった気持ちを持つ事によって、ゆとりを持って子供に接する事ができます。
逆に「敗北感」を感じて子供に接するとどうでしょう? 極端なケースになると、自分を敗北者に追いやった原因である子供に憎しみさえ感じられるケースもあるのだそうです。
もともとは自分でも、そんなにまで高い理想を掲げていたわけではなかったのに、姑や母親、先生や医者、近所の人や会社の人などのアドバイスや中傷、本で読んだり人に聞いたりしてできあがる価値観などによって、いつの間にか他人からのプレッシャーに操られてしまい、自分で自分を苦しめてしまうのです。
特に真面目で教育熱心な人がこの罠にはまる事が多く、ヘビのトグロのように縛り付けられてしまいます。
私もその昔、1歳までにオムツを取ったという姑と義姉からさんざん責め立てられ、幼稚園の入園までに取らなければと焦って、「おだてても駄目ならぶつしかない」と、毎日特訓を続けたのですが、どうしても取れなくて、焦りと敗北感で疲れ切ってしまいました。
ところが、できないものは仕方がないと、ついに諦めて幼稚園の入園を遅らせて欲しいと電話を入れた途端、信じられないほど簡単に歩ロッとおむつが取れてしまいました。
それまでは「うちの子はこれもまだできない、あれも遅れている」と、できない事ばかりに目が行っていたものが、私自身が焦りと執着を捨てることによって、「昨日できなかった事が今日はできるようになった」と、できりょうになったという事実の方に注目でき、褒めてあげる事が増えた為、子供も敗北感から解放されて自由な成長を遂げられたのだと思います。
私自身も「偉い母親」より「幸せなお母さん」でいる方が自分にはあっているので、ずっとラクになりました。
よくよく考えてみると、実はご主人がプレッシャーを与える最大の原因となっていた、、とい場合もあるようです。妻にばかり責任を押し付けて追い詰めず、夫婦でよく話し合い、協力しあうことが何よりも大切です。
私もこのセミナーをきっかけに夫と話し合って、我が家では私達の理想像を「頭がよいとか、いい子だとかいう条件付きではなく、子供をあるがままに愛する」、「子供からのサインを敏感にキャッチする」、「一人の人間として子供の人格を尊重する」という3点に絞りました。
人それぞれの考え方や価値観、性格などによって各家庭で理想とするものは異なると思いますが、夫婦がよく話し合って協力し合い、同じ方向に一緒に歩んでいれば、子供は安定して成長していくものではないかと思います。
まずは自分がはあってしまっている罠に自分で気づき、自分をその罠から解放してあげることから始めましょう。あなたを裁いているのは他でもない、あなた自身なのかも知れません。
世に言われる「理想的な母親」というのは、具体的にどんな要素が上がるでしょうか?
「常に子供がお行儀がよく親の言う事をきく」、「常に規則正しい生活をさせる」、「早く読み書き勘定ができるようにさせる」、「常に子供と一緒にいる」、「早くおむつをはずさせる」、「離乳食はすべて手作り」、「母乳だけで育てる」など色々と挙げられますが、これらのすべてを実際に実行なさっている方がいらしたら、その方はそれこそ偉大です。
私はと言えば、全部が失敗。私なりにがんばったのですが、やっぱり無理でした。「理想」実行できない事を「失敗」と呼びますが、この「敗北感」が「理想的な母親像」という名の罠に陥る最大の原因となるのだそうです。
もう一度、理想像の要素を振り返ってみましょう。「常に」とか「絶対に」ではなく、「できるだけ」とか「なるべく」という言葉を添え直してみると、自分でも何とか達成できていた事も増えるのではないでしょうか?
この「達成感」が大切なのだそうで、「この位できれば、まあいいか」とか「できなかったけど、人生、このくらいの事は重大な過失ではないから、まあいいか」といった気持ちを持つ事によって、ゆとりを持って子供に接する事ができます。
逆に「敗北感」を感じて子供に接するとどうでしょう? 極端なケースになると、自分を敗北者に追いやった原因である子供に憎しみさえ感じられるケースもあるのだそうです。
もともとは自分でも、そんなにまで高い理想を掲げていたわけではなかったのに、姑や母親、先生や医者、近所の人や会社の人などのアドバイスや中傷、本で読んだり人に聞いたりしてできあがる価値観などによって、いつの間にか他人からのプレッシャーに操られてしまい、自分で自分を苦しめてしまうのです。
特に真面目で教育熱心な人がこの罠にはまる事が多く、ヘビのトグロのように縛り付けられてしまいます。
私もその昔、1歳までにオムツを取ったという姑と義姉からさんざん責め立てられ、幼稚園の入園までに取らなければと焦って、「おだてても駄目ならぶつしかない」と、毎日特訓を続けたのですが、どうしても取れなくて、焦りと敗北感で疲れ切ってしまいました。
ところが、できないものは仕方がないと、ついに諦めて幼稚園の入園を遅らせて欲しいと電話を入れた途端、信じられないほど簡単に歩ロッとおむつが取れてしまいました。
それまでは「うちの子はこれもまだできない、あれも遅れている」と、できない事ばかりに目が行っていたものが、私自身が焦りと執着を捨てることによって、「昨日できなかった事が今日はできるようになった」と、できりょうになったという事実の方に注目でき、褒めてあげる事が増えた為、子供も敗北感から解放されて自由な成長を遂げられたのだと思います。
私自身も「偉い母親」より「幸せなお母さん」でいる方が自分にはあっているので、ずっとラクになりました。
よくよく考えてみると、実はご主人がプレッシャーを与える最大の原因となっていた、、とい場合もあるようです。妻にばかり責任を押し付けて追い詰めず、夫婦でよく話し合い、協力しあうことが何よりも大切です。
私もこのセミナーをきっかけに夫と話し合って、我が家では私達の理想像を「頭がよいとか、いい子だとかいう条件付きではなく、子供をあるがままに愛する」、「子供からのサインを敏感にキャッチする」、「一人の人間として子供の人格を尊重する」という3点に絞りました。
人それぞれの考え方や価値観、性格などによって各家庭で理想とするものは異なると思いますが、夫婦がよく話し合って協力し合い、同じ方向に一緒に歩んでいれば、子供は安定して成長していくものではないかと思います。
まずは自分がはあってしまっている罠に自分で気づき、自分をその罠から解放してあげることから始めましょう。あなたを裁いているのは他でもない、あなた自身なのかも知れません。